- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.15
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. 初見で弾く練習は、どういう方法で取り組むべき?
- ‣ Q2. ダウンロード購入した楽譜の製本のコツが知りたい
- ‣ Q3.「ここは運指を直さないで」と先生から言われたが、弾きにくい場合はどうすべき?
- ‣ Q4. 自分のレベルで明らかで弾きやすい楽曲をレッスンでお願いしてもいい?
- ‣ Q5. 曲の背景を知るために、作曲家の書簡や日記を読むことは有効?
- ‣ Q6. 先生に「いつか作曲に挑戦したい」という目標を伝えても、困らせない?
- ‣ Q7. 先生から「この曲は難しいからやめたほうがいい」と言われたら、従うべき?
- ‣ Q8. 弾き終わった後、先生のコメントが出るまでの「間」が怖い
- ‣ Q9. 発表会のプログラムに書かれている自分の名前や曲名に間違いがあったら、先生に指摘すべき?
- ‣ Q10. 先生のレッスンで教わったことを、他人に教えるのはアリ?
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.15
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. 初見で弾く練習は、どういう方法で取り組むべき?
結論:段階的かつ継続的に、様々なアプローチで
初見力は一朝一夕には身につきませんが、以下のような多角的な練習を継続することで確実に向上します。
効果的な練習方法:
・片手のみでの初見練習 – 右手または左手のみで
・初見で暗譜して演奏する練習 – 楽譜を短時間見た後、記憶を頼りに演奏(記憶力と読譜力を同時に鍛える)
・緩徐楽章を活用 – ゆっくりで真っ黒な楽譜は、初見練習に最適
・新曲を初見教材に – 新しく取り組む作品の第一回目を、意識的に初見練習の機会にする
・音楽雑誌の楽曲で練習 – クラシックに少ないリズムパターンへの慣れに効果的
重要な心構え:
・一旦最後まで行くまでは、弾き直さない(流れを止めずに進む訓練)
・できるようにならないのは、やらないから
・初見練習のためのスペシャルな時間を継続して確保する
・初見演奏ができないだけで、生涯に触れられる作品数が圧倒的に減ってしまうことを理解する
推奨記事:【ピアノ】初見演奏のテクニックと練習法:上達のコツ 12選
‣ Q2. ダウンロード購入した楽譜の製本のコツが知りたい
結論:蛇腹製本を避け、紙のマスキングテープで段差のない仕上がりに
ダウンロード楽譜を美しく、かつ使いやすく製本するには、いくつかのポイントがあります。
製本のポイント:
・蛇腹製本は避ける – 譜めくりで特定のページを引っ張ると、全体が大きな輪っか状に広がってしまう
・紙のマスキングテープを使用 – セロハンテープは貼り直しができず、経年劣化でかなり黄ばむ
・背表紙の仕上げ – マスキングテープでも良いが、背ばり用の幅広テープを使うとより本格的
具体的な製本の手順やテープの選び方は、【ピアノ】クオリティ重視の楽譜製本術:蛇腹製本からの卒業で詳しく紹介しています。
‣ Q3.「ここは運指を直さないで」と先生から言われたが、弾きにくい場合はどうすべき?
結論:弾きにくさを感じなくなるまで、その運指で練習を重ねる
「運指を直さないで」という指示には、必ず重要な学習意図があります。
なぜ、その運指が指定されるのか
例えば、ゆっくりのテンポでは弾きやすい運指でも、本来のテンポでは全く対応できなくなってしまうケースがあります。目先の弾きやすさを優先すると、大切な技術習得の機会を逃し、後々さらに苦労することになります。
対応の手順:
・まずは、指定された運指で丁寧に反復練習
・それでもどうしても演奏できない場合は、再度指導者に相談
・その際、「なぜこの運指が推奨されるのか」を必ず確認
理由を理解することで、納得して練習に取り組めます。
‣ Q4. 自分のレベルで明らかで弾きやすい楽曲をレッスンでお願いしてもいい?
結論:全く問題ない。むしろ、音楽的な深みを学ぶ良い機会に
自分の実力よりも相当高いレベルの大曲ばかりに取り組んでいても、深い音楽観は育ちません。
シンプルな作品を学ぶ意義
シンプルな作品は音数こそ少ないのですが、美しく仕上げるのは簡単ではありません。ちょっとでも音を出し急いだり、生々しいダイレクトな音を出してしまうと、一気に台無しになってしまうような繊細な音楽はたくさんあります。
おすすめのアプローチ:
・モーツァルトの緩徐楽章などでシンプルな音楽を本当に音楽的に仕上げる
・「2ランク程度易しい」選曲をする(例:全音ピアノピースでいう、ランクDに普段取り組んでいる方はランクBを)
選曲の参考リソース
本Webメディアではレベル別おすすめ楽曲カテゴリーを用意しています:
・おすすめの楽曲(初級)
・おすすめの楽曲(初中級)
・おすすめの楽曲(中級)
・おすすめの楽曲(上級)
中級者以降に特におすすめの教材
ツェルニー40番以上の学習段階にいる方があえてシンプルな作品に取り組む場合は、クララ・シューマンが編曲した「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」の中から、ツェルニー30番入門程度の作品をチョイスするのもおすすめです。原曲が歌曲なので、シンプルながら深い表現を特徴としている作品揃いです。
【ピアノ】クララ編「ロベルト・シューマンの30のリートと歌」取り組みやすい11曲 完全ガイド
‣ Q5. 曲の背景を知るために、作曲家の書簡や日記を読むことは有効?
結論:非常に有効。ただし、即座に演奏に反映されると期待し過ぎない
作曲家の書簡や日記を読むことで、作曲家の人となりや作品の背景を知ることができ、とても良い学習方法です。
学習効果
こういった背景情報を知ることも含めて、音楽学習を楽しめるようになると、学びの質が大きく変わります。「リズムと音の高さだけを読んで満足する学習」から一歩抜きん出ることができます。
注意点
ただし、読んだ内容がそのままダイレクトに演奏に活かせると期待し過ぎないようにしましょう。背景知識は、長い時間をかけて音楽理解の土台となっていくものです。
おすすめの読み物:
・シューマン、ドビュッシー、シェーンベルク、武満徹などの評論集
・レベル別:ピアノ独学者のための学習参考書籍ライブラリー で紹介
‣ Q6. 先生に「いつか作曲に挑戦したい」という目標を伝えても、困らせない?
結論:目標を伝えるだけでなく、小さくても実際に始めることが大切
正直に言うと、「いつかやりたい」という相談は、先生を少し困らせる可能性があります。
なぜ、困らせるのか
本当にやりたい人は、自分なりに細々とでもすでに始めています。「またやらないことのためにアドバイスするのか」と思われる可能性があるためです。筆者は、「いつかやりたい」と言っていて本当にやる人をほとんど見たことがありません。
ピアノを弾ける方にとって、作曲を始めるのに準備は不要
より高いクオリティで創作するために学ぶべきことはありますが、もう始められる状態にあります。
おすすめのアプローチ
「いつか作曲に挑戦したい」ではなく、「作曲に挑戦してみています。次の発表会で披露していいですか?」くらいの、一歩進んだ相談をしましょう。
実際に小さな作品を作ってみたうえでの相談であれば、先生も具体的なアドバイスができ、生徒側も実りある学習ができます。
‣ Q7. 先生から「この曲は難しいからやめたほうがいい」と言われたら、従うべき?
結論:理由を丁寧に聞き、代案も提案してもらう
「この曲は難しいからやめたほうがいい」と言われるケースでは、主に以下の状況が考えられます。
先生の判断理由(例):
・学習負荷が高過ぎて、時間がかかる割には学習効果が上がらない
・その生徒のこれまでの姿勢から見て、やり抜けずに失敗体験になる可能性が高い
・今のテクニックの習得状態で無理に弾くと、手の故障を招く可能性がある
推奨される対応:
・まずは理由を聞く – 「なぜ、この曲は今の私には難しいのでしょうか?」
・代案を提案してもらう – 「では、同じような雰囲気で今の私に適した曲はありますか?」
・将来の可能性を確認 – 「どのくらい学習を積めば挑戦できそうですか?」
代案に納得できれば、お互いに心穏やかに学習を進めることができます。
‣ Q8. 弾き終わった後、先生のコメントが出るまでの「間」が怖い
結論:明かな準備不足やマナー的な不義理でがっかりさせなければ、何も怖くない
なぜ「間」が怖く感じるのか:
・評価を待つ緊張感
・沈黙=否定的な反応かも、という思い込み
先生が黙っていると「何か悪かったのかな」と思ってしまいがちですが、多くの場合、先生は「どこをどう伝えようか整理している」だけです。
何のためにレッスンに通っているのかを考える
もちろん、褒めてもらえたり肯定的な意見をもらえると嬉しいに決まっています。しかし、先生に褒めてもらうためだけにお金と時間を使っているわけではないはずです。
正当な指摘が入るのであれば、むしろプラスになることのほうが圧倒的です。きちんと準備をしてレッスン日を迎えたのであれば、心配する必要はありません。
心配しなくて良いケース:
・真面目に練習してきた
・レッスンのマナーを守っている
・分からないことは素直に質問している
明らかな準備不足やマナー的な問題でがっかりさせなければ、何も怖くありません。
重要なポイント
「間」が怖く感じても、演奏後に自分から一方的に喋りすぎてはいけません。「あそこが難しくて…」「ここは時間が足りなくて…」と言い訳を並べるのは避けましょう。演奏後のバトンは、一旦先生に渡っていることを忘れずに。
‣ Q9. 発表会のプログラムに書かれている自分の名前や曲名に間違いがあったら、先生に指摘すべき?
結論:本番当日の読み上げに影響するため、必ず指摘する
自分の名前や曲名に誤りがある場合は、発見した段階(仮プログラム、完成後を問わず)で必ず指摘しましょう。
指摘すべき理由:
・名前の誤り – 先生が勘違いしている場合、今後も繰り返される可能性がある
・曲名の誤り – 当日の司会による読み上げで誤った情報が伝わる
・記録として残る – プログラムは記念として保管されることが多い
段階別の対応方法:
仮プログラムの段階
「お手数ですが、〇〇の部分を修正していただけますでしょうか」とストレートに伝える
完成したプログラムの場合
「プログラムはこのままで構いませんが、当日の読み上げの際には正しく読んでいただけますか」と依頼
当日の確認
心配であれば、当日にもう一度、正しい読み上げをお願いしても構いません。先生にしつこく感じられる可能性はありますが、読み上げを担当する方に伝わっていなかったケースは時々耳にします。
‣ Q10. 先生のレッスンで教わったことを、他人に教えるのはアリ?
結論:自分で消化した内容を、自分の言葉で伝えるのであれば、むしろ推奨
インプットした内容を適切にアウトプットするのは、とても良い学習になります。教えることで、自分の理解も深まります。
ただし、守るべきポイント:
自分の言葉で説明する
先生が言ったことを「こう言っていたから」とそのまま伝えるのではなく、自分なりに噛み砕いて説明する
実践した内容のみ伝える
きちんと自分で実践して身になった内容のみアウトプットする
口調に注意
先生に言われた口調まで真似すると、友人同士の場合マウンティングのように響く可能性がある
録音の扱い
仮にレッスンを許可を得て録音していたとしても、それをそのまま他人に渡すのは絶対に避ける
伝え方の例:
良い例: 「私が習った方法なんだけど、こういう練習が効果的だったよ」
避けるべき例: 「先生が〇〇って言ってたから、あなたもそうすべきだよ」
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
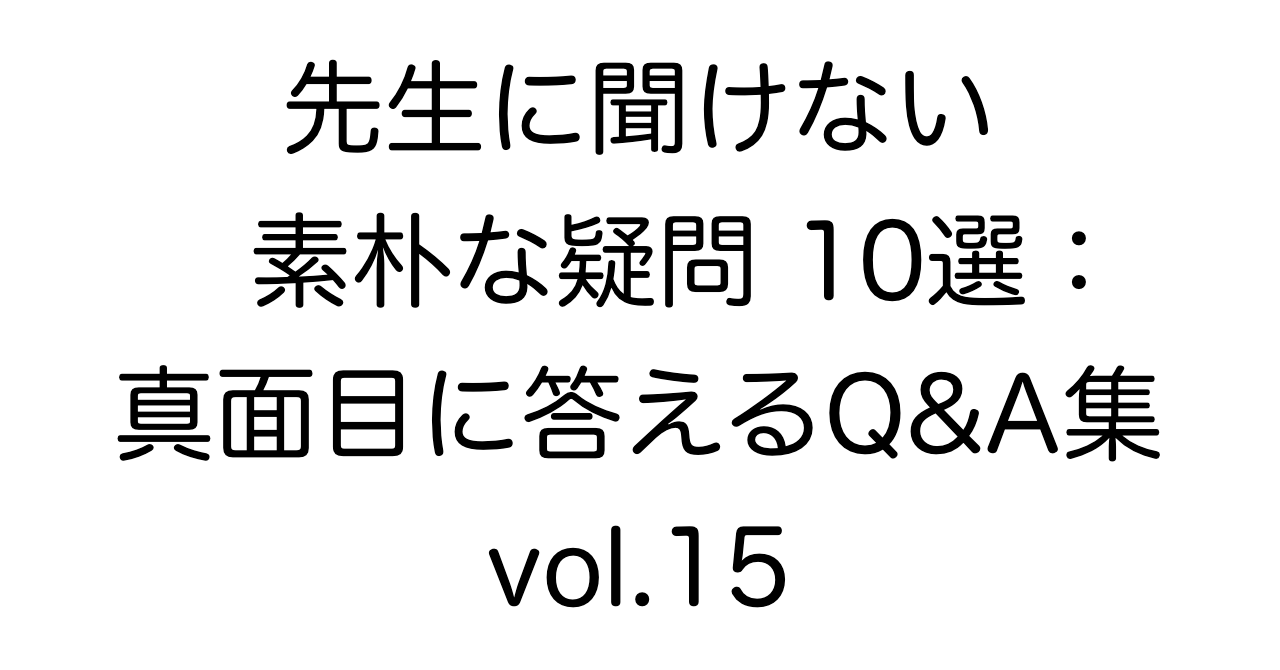
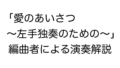
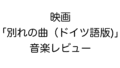
コメント