【ピアノ】映画「ピアニスト(La Pianiste)」レビュー:音楽演出と心理描写の関係性を解析
► はじめに
映画「ピアニスト(La Pianiste)」は、ピアノを通して出会った人間の精神の闇を探求する作品です。音楽と感情の複雑な関係について考えさせられる内容となっています。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:2001年(フランス)/ 2002年(日本)
・監督: ミヒャエル・ハネケ
・ピアノ関連度:★★★☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。
‣ 音楽による明確な物語構造
本作で最も注目すべき音楽演出は、物語を音楽の「有無」で明確に区分している点です。映画の前半は音楽院でのレッスンシーンや演奏シーンが豊富に登場し、クラシック音楽が重要な役割を果たしています。特にシューベルトの「ピアノソナタ 第20番 D 959 第2楽章」がワルターによって演奏された後、後半45分間はピアノ演奏シーンが一切なくなり、BGMさえも消え去ります。
この音楽構成には深い意味があります。前半の「音楽のある世界」は、エリカの表の顔—音楽院教員としての厳格な姿—を象徴し、後半の「音楽のない世界」は彼女の内面の闇と混沌を表していると考えられるでしょう。特に、ラスト30分間のテレビから間接的に聴こえてくる音楽さえも排除した完全なる音楽の不在は、エリカの精神的崩壊と共鳴するように感じられます。ストーリー的にも、ラストでエリカは音楽から離れてしまいます。
‣「明らかに状況内音声と分かる音」からの表現の拡大
序盤、弦楽器を調絃する音が聴こえはじめる場面は、音楽の使い方の巧みさを表しています。
この段階では映像に弦楽器が写っているわけではありませんが、調絃というのは「明らかに状況内音声と分かる音」なので、聴衆に弦楽器を想像させます。その後、やはりバイオリンとチェロが映し出されて、映像的にも状況内音声であったことが説明されます。やがて、ピアノ・バイオリン・チェロで演奏していた、シューベルト「ピアノ三重奏曲 第2番 D 929 第2楽章」の音声をそのまま残して別の場面に変わります。この時点で状況外音楽へ変化したことになります。
面白いのは、通常、状況外音楽のBGMとして鳴っていたら場面に合わないようなテイストの音楽であっても、このように状況内音楽で聴かせておいた後に移行させた場合は、違和感なく状況外音楽として聴けるということです。
‣ 序盤にとられた、物語のクライマックスへの音楽的伏線
その後、この状況外音楽(上記、シューベルトのピアノ三重奏曲)を、テレビから聴こえてくる全くジャンルの異なる状況内音楽と数秒オーバーラップさせる演出も見られます。そして、クラシック音楽がかき消されるかのように、シューベルトが突然カットされるのです。
本編序盤に見られるこの「タイプの全く異なる音楽がクラシック音楽をかき消す」という演出は、すでに物語のクライマックスの伏線になっていると考えることができるでしょう。主人公エリカの音楽的世界観が外部の力によって侵食されていく過程を暗示しているのです。
► 終わりに
「ピアニスト」は、音楽と人間心理の複雑な関係を描く作品です。音楽の使用と不使用を対比させることで、主人公の内面の分裂を表現する手法は見事であり、音楽が持つ力と、それを失った時の空虚さを再認識させてくれるでしょう。
ただし、本作には過激な描写が多く含まれるため、視聴の際にはご注意ください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
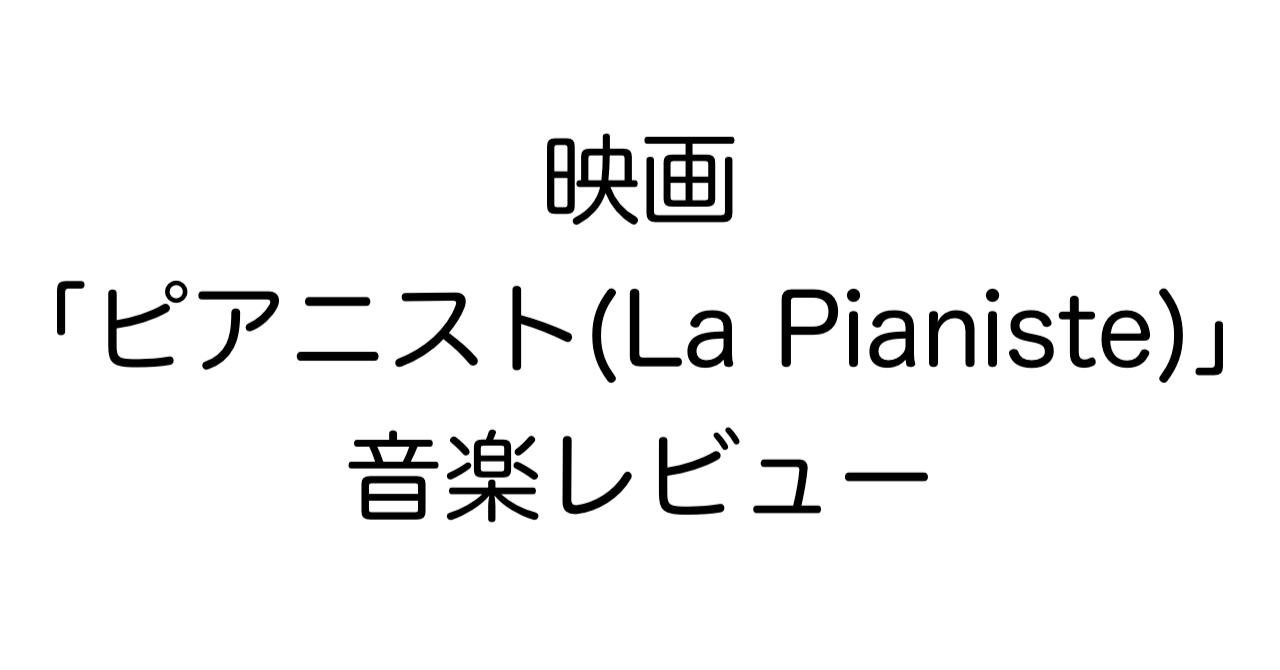

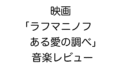
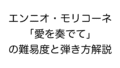
コメント