【ピアノ】音楽に関する心配事との付き合い方
► はじめに
ピアノを含む音楽の学習過程では、様々な不安や心配事が付きまといます。「譜読みが間に合わない」「本番で失敗するかも」「上達しているのか分からない」など、心配の種類は人それぞれでも、誰もが経験する感情でしょう。
本記事では、音楽に関する心配事との効果的な付き合い方について取り上げます。
► 心配事の種類に応じた対処法
‣ 1. 短期的かつ、それなりに対処可能な心配事
「コンサートまでに譜読みが間に合わない」「レッスンまでに仕上げられない」など、期限が迫っている心配事は、とにかく、先延ばしにせず最優先で対処することが大切です。1日〜数日程度、全力で対処して間に合いそうな事であれば、心配している時間を使ってでも何とかしましょう。
一方、心を持っていかれる原因が音楽以外(来客準備の不用意など)にある場合は、「音楽へ手をつける前に」まずそちらを解決することが先決です。そうしないと、常に常に集中力を持っていかれてろくな学習ができないからです。
‣ 2. 将来に対する心配事
楽器の不調や故障に関する心配
ピアノの音が変だと感じたり、不具合を感じたりした場合は、「とりあえず一手を進めること」が重要です。調律師さんにアポを取るだけでも、「とりあえず解決へ向けて動いている」という安心感が生まれ、余計な心配をいったん頭から離すことができます。
演奏会やコンクールの成功に関する心配
完璧な演奏は存在しないことを前提に、「時間をかけた」と思えるところまでは、練習やら対策やらをやっておくといいでしょう。「時間をかけた」と思えていない段階では、仮に当日そこそこうまくいったとしても何だか後味が悪く、本番までの過程における収穫も少ないものです。
‣ 3. 自分でコントロールできない心配事
審査結果を待つ時間や、他者の判断に委ねる状況では、どうしても心配や不安が募りがちです。そんな時は、あえてとことん悩んでおいて、その経験を他者との会話やブログのネタにしましょう。本記事ですら、つい最近筆者自身に自分でコントロールできない心配事があったからこそ、改めてこうして整理して紹介しているわけです。
► 心配事への向き合い方
‣ 心配の先にあるものを想像してみる
心配を完全に「忘れよう、忘れよう」と思っても、そもそもムリ。むしろ、その心配が現実になった場合、どうなるのかを一度真剣に考えてみましょう。意外と「そこまで深刻ではない」と気づくケースが多いものです。
1年前に何を心配していたか覚えていますか?多くの場合、当時は大きく感じた心配事も、時間が経つと些細なことだったと感じるものです。この視点を持つだけでも、現在の心配事への心の持ち方が変わってきます。
‣ 音楽から学ぶ心配との付き合い方
音楽に関する心配で心を悩ませた経験は、日常生活の様々な場面にも活かせます。上記のような心配事への対処法によって、似たような状況に遭遇した際にも冷静に対応できるようになるでしょう。
►「対処する」と「待つ」のバランス
音楽の学習において、「対処する」ことと「待つ」ことの両方が重要です。この二つは一見矛盾するようにも思えますが、実は相補的な関係にあります。
‣「対処する」—今すぐできることに取り組む
これまで見てきたように、譜読みの遅れや楽器の不調など、具体的なアクションで解決できる問題には積極的に対処することが大切です。必要な手段を講じることで心が落ち着き、適度な距離でその心と付き合えるようになります。
‣「待つ」—プロセスを信じる
一方で、音楽的な成長や技術の習得には時間がかかるものです。「待つ」とは、単に何もせずに時間が過ぎるのを待つことではなく、「目の前すぐの状態でものごとを判断しない」という姿勢を持つことだと思ってください。
例えば、コンクールですぐに結果が出ないと指導者のせいにして即刻クレームを入れる、というケースがあります。また、「これでいいのか、これで上手くなるのか」と心配し過ぎて毎日のように指導者へ連絡を入れるというケースも見られます。
こうした状況で大切なのは、「やることはしっかりとやりながら、待つ」という姿勢です。確実に言えるのは、その人にはその人の良くなり方があるということ。
筆者の知り合いには、ピアノに関して18歳まで大きな伸びがこなかったものの、その年に驚くほどの成長を遂げ、周囲を驚かせた人物がいます。現在は誰もが知る著名なピアニストになりました。
趣味で演奏している方も同様です:
・書籍に書いてあった普段とは別の角度からの言葉が腑に落ちた瞬間に、技術的なことまでついてくるようになった
・指導者がそばへ行って踊ったら、カチカチだった身体が柔らかくなってコツをつかんだ
何がきっかけで学習が前進するかは誰にも分かりません。急激な前進ばかりではなく、亀の歩みのように徐々に伸びていく学習者もいます。
‣「対処」と「待機」の賢明な使い分け
「損切り」という言葉があるように、何の試行錯誤もなく同じことを長期間続けても意味はありません。しかし、何かしらの試行錯誤をしている限り、「目の前すぐの状態でものごとを判断せずに待つ」という基本姿勢が大切です。
具体的には:
対処すべき時:明確な期限がある、解決策が見えている、自分の責任範囲である
待つべき時:長期的な成長に関わる、複雑な要素が絡む、自分の努力以外の要素に依存する
► 終わりに:心配事を味方につける
音楽の学習における心配事は、対処法を知り、適切に向き合うことで、むしろ成長の糧となります。心配事そのものを悪いことだと思わないようにしましょう。短期的に対処できることには積極的に取り組み、長期的な成長プロセスに関しては「やることはやりながら待つ」という姿勢を持つことが重要です。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
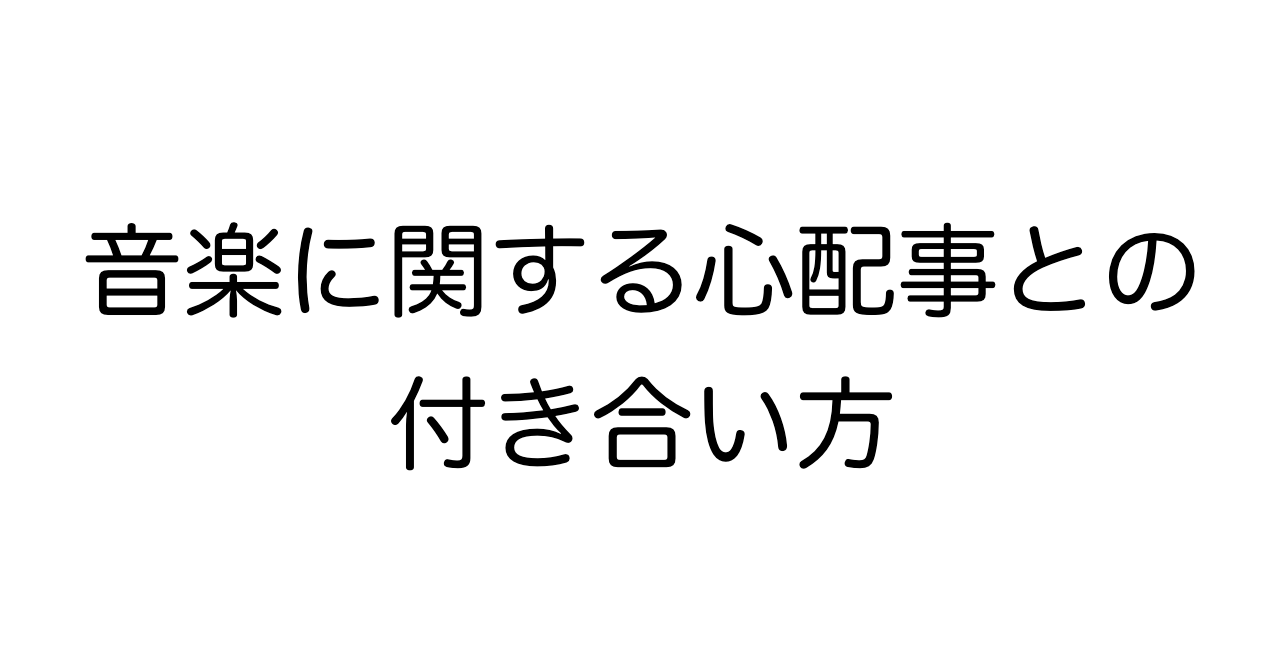
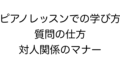
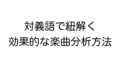
コメント