【ピアノ】自分が視覚的な要素と聴覚的な要素のどちらを得意としているのかを考える
► はじめに
様々な音楽書籍を読んだり、力のある音楽家の話を耳にしたりしていると、練習方法や学習方法に「視覚的要素」と「聴覚的要素」の両面のアプローチが見られます。
本記事では、自分がどちらに強いタイプなのかを考え、より効果的な練習法を見つけるヒントを提供します。
► 演奏の例:視覚的要素と聴覚的要素の違い
例えば「暗譜」であれば、視覚的要素を重視したものでいうと、「楽譜を景色で覚える」などといった方法が取り上げられています。聴覚的要素を重視したものでいうと、「和声を把握して覚える」などといった方法が見られます。
両方の要素に長けている場合はともかく、こういった方法をいくつも試してみると、「視覚的要素を重視したアプローチではあまり効果が上がらず、聴覚的要素を重視したものだと効果が上がる、もしくはその逆」などという傾向が見えてくる可能性があります。
人によってどちらの要素に強いかは我々が思っている以上にはっきり出ます。「どちらがいいか」ではなく、自分の特性を知ったうえで、自分にとって有効なアプローチに力を入れていくといいでしょう。世の中に出回っている練習アプローチや学習アプローチを眺めてみると、大抵、視覚か聴覚のどちらかを重視したものに分類できます。
► 創作の例:視覚的要素と聴覚的要素の違い
演奏だけでなく、作曲や編曲においても視覚的要素と聴覚的要素の違いは顕著に表れます。それぞれのタイプがどのように創作に影響するかを考えてみましょう。
視覚的要素に強い人物は、楽譜を書くにあたって、本当に細かなレイアウトのズレや書法の美しさに気が向くので、仮にそれほどテクニックが高くなくても、本当に綺麗な譜面を書きます。また、こういった人物は、学習する時も、目で吸収する量が多くなります。
聴覚的要素に強い人物は、レイアウトなどには大雑把でも、それを演奏した時に出てくる音は綺麗です。こういった人物は、学習するときも、耳で吸収する量が多くなります。
► 終わりに:自分の特性を知り、活かす
筆者の出会ってきた人物で言うと、視覚的要素に長けている人物には、どちらかというと真面目で細部に注意を払えるタイプの方が多かったように感じます。一方、聴覚的要素に長けている人は、全体の流れや音の調和に敏感な傾向があります。
繰り返しますが、「どちらがいいか」ではなく、自分の特性を知ったうえで、自分にとって有効なアプローチに力を入れていくといいでしょう。大抵、自分の強みと反対の要素にコンプレックスを持ってしまうものなので、そればかりになると、重要な成長機会を捨ててしまうことになります。反対の要素を伸ばす必要があるのは、弱い部分が強い部分に対するボトルネックになっている場合のみです。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
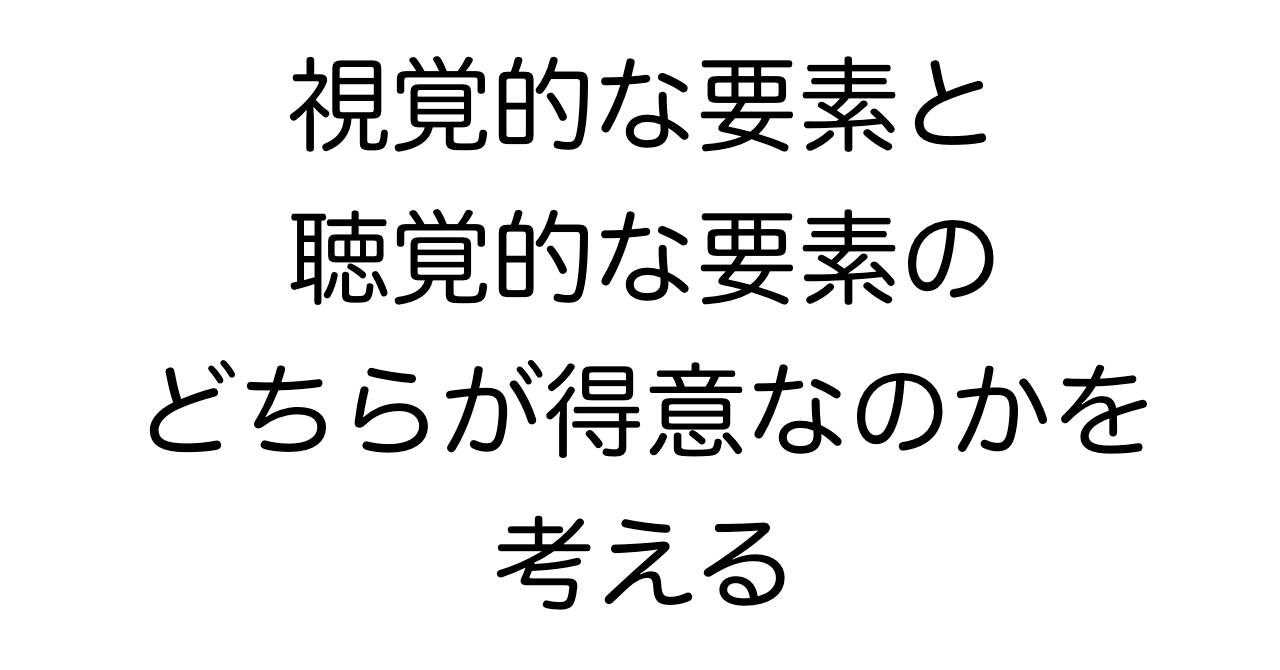
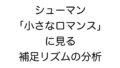
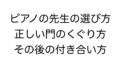
コメント