【ピアノ】分散和音の見分け方:J.S.バッハ作品を例に
► はじめに
分散和音の分析は、楽曲の構造を理解するうえで重要な要素の一つです。
本記事では、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」を用いて、分散和音の見分け方と分析方法を解説します。
前提知識:
・基本的な和声(Ⅰ、Ⅳ、Ⅴなど)の理解
・音程と和音の基礎知識
・転回形の概念
► 分散和音の分析の基礎
‣ 分析対象と基本情報
J.S.バッハ「アンナ・マクダレーナ・バッハの音楽帳 第2巻 メヌエット BWV Anh.116」
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、1-8小節)
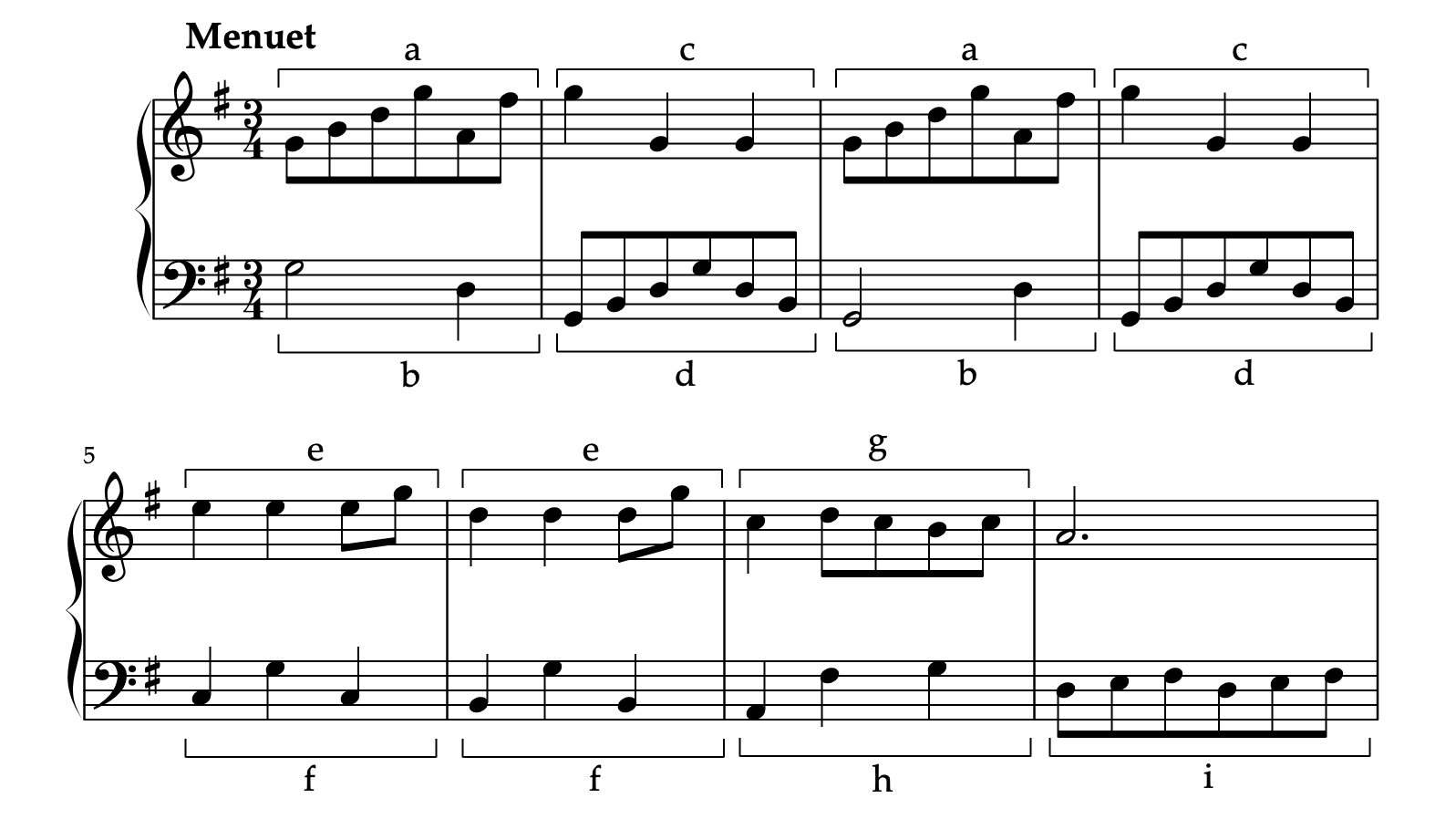
譜例で示したカギマークは解説のための小節区分であり、音楽的な構成単位を示すものではありません。
‣ 詳細分析
分散和音の判断基準:
・和声進行の把握
・音の動きのパターン(順次進行か跳躍進行か)
・両手で弾く音をあわせた時に形成される和声
各部分の特徴を見ていきましょう:
1-4小節
a:分散和音
・1-2拍目と3拍目で異なる和声を形成
・どちらも和音構成音のみで構成
b:分散和音ではない
・左手パートのみを見るとG-durの主和音の分散和音にも見えるが
・右手パートを考慮すると、3拍目のD音はⅤの根音だということが分かる
c:分散和音
・オクターブ跳躍している
・左手パートより、和声はG-durの主和音である
これら2つの条件が揃っているので、分散和音の一種。和音が変わっている場合は、オクターヴ跳躍していても分散和音とは言えないケースもあります。
d:分散和音
・G-durの主和音における分散和音
5-8小節
e:分散和音
左手パートを考慮すると:
・5小節目はⅣ
・6小節目はG-durの主和音の第一転回形
つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。
f:分散和音
右手パートの音と合わせると:
・5小節目はⅣ
・6小節目はG-durの主和音の第一転回形
つまり、和声音しか使わずに分散させていると分かります。
g:分散和音ではない
非和声音も用いながら順次進行で動いているので、分散和音ではありません。
h:分散和音ではない
一見、分散和音かと思うかもしれませんが、2拍目→3拍目の部分で順次進行があるので、その部分は分散和音ではないことが分かります。1拍目→2拍目は分散しているように見えますが、ここでは右手の音も考慮すると:
・1拍目:Ⅱ
・2拍目:属七の第一転回形
・3拍目:Ⅰ
となっているので、1拍ごとに別の和声のバスということになります。
i:分散和音とそうでないところの混在
右手パートも考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。
演奏への活用:
・分散和音の部分は、和声感を感じなから弾く
・左手パートに出てくる分散和音では、バス以外の音がバス音よりも大きくならない
・順次進行の部分は、重くならないように通り過ぎる
‣ 分析の実践演習
同曲の別箇所を使って、分散和音とそうでない部分の区別をしてみましょう。
譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、25-28小節)
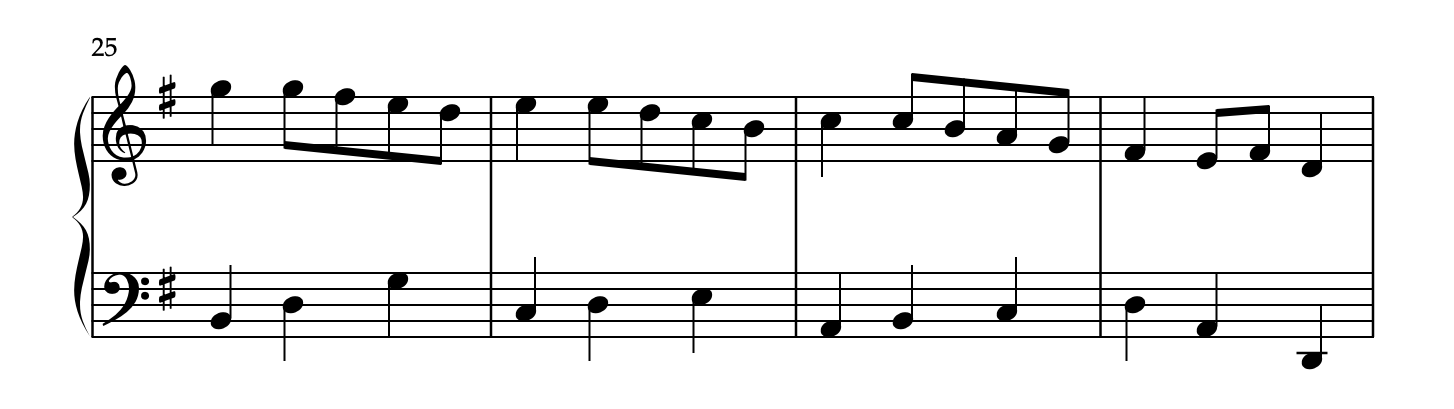
分析の着眼点:
・順次進行と跳躍進行の識別
・和声の把握
・両手の相互関係の理解
解答例と解説
・25小節目の右手パート:順次進行なので、分散和音ではない
・26-27小節の右手パート:25小節目の同型反復なので、同様
・28小節目の右手パート:分散和音とそうでないところの混在
・25小節目の左手パート:分散和音(G-durの主和音の第一転回形)
・26-27小節の左手パート:順次進行なので、分散和音ではない
・28小節目の左手パート:分散和音(G-durのⅤ)
28小節目は、それぞれのパートを考慮するとⅤだと分かります。Fis音→D音の部分は分散和音ですが、それ以外の部分は順次進行なので分散していません。
► まとめと応用
この分析手法が特に有効な楽曲:
・機能和声に基づく作品
・バロック~古典派の作品
発展的な学習方向:
・和声分析との組み合わせ
・様式研究への応用
・他の時代・作曲家での実践
【おすすめ参考文献】
本記事で扱った、J.S.バッハ「メヌエット BWV Anh.116」について学びを深めたい方へ
・大人のための独学用Kindleピアノ教室 【J.S.バッハ メヌエット BWV Anh.116】徹底分析
【関連記事】
▶︎ 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら
楽曲分析学習パス
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
・SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
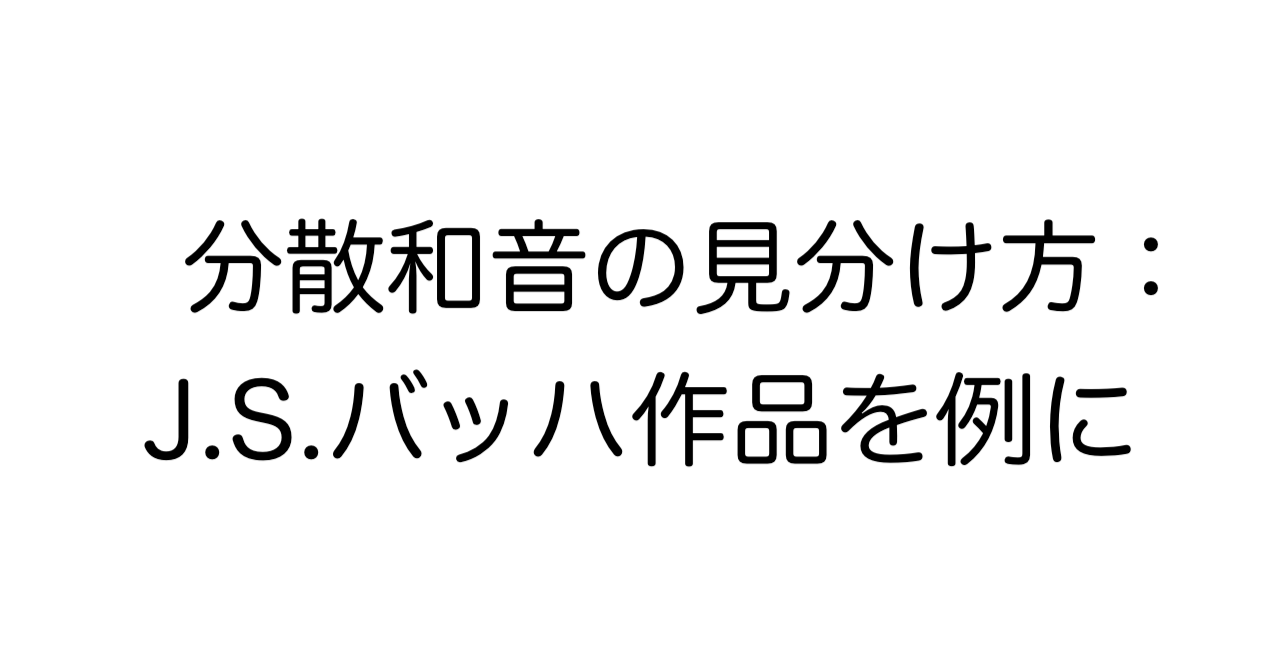



コメント