【ピアノ】レッスンでの学び方・質問の仕方・対人関係のマナー
► はじめに
本Webメディアでは「独学」を前提とした記事を提供していますが、時に指導者の的確なアドバイスがあると飛躍的に成長できることがあります。スポットレッスンや短期間の指導を受けることで、独学では気づきにくい点を効率よく補完できるでしょう。しかし、せっかくのレッスンを最大限に活かすには、適切な姿勢とマナーを身につけることが重要です。
本記事では、ピアノレッスンを受ける際の基本姿勢、効果的な質問の仕方、そして教室での対人関係におけるマナーについて解説します。これらのポイントを意識することで、レッスンから得られる学びを最大化し、指導者との良好な関係を築くことができるでしょう。
独学をメインにしている方も、時々レッスンを受ける方も、本記事を参考にして欲しいと思います。
► A. レッスンにおける基本姿勢
‣ 横で弾く指導者の演奏をよく聴く
ピアノレッスンでは「先生が絶対的に偉い」というわけではありません。だからといって、「レッスン代を払っているのだから、生徒が偉い」というわけでもありません。
それを前提としてではありますが、習いにくる生徒に指導者がアドバイスをしていく形式をとっている以上、やはり、まずは指導者の演奏と話に耳を傾けてみる姿勢が必要だと思うのです。
その点で気になるのが、アドヴァイスとして横で弾き示している先生の演奏と言葉をさえぎるかのように、生徒が演奏を再開してしまうこと。
レッスンのあり方は教室それぞれですが、基本的にはレッスンというのは、上手に弾けるということを先生に分かってもらうためのデモンストレーションではありません。次々に弾き進めて先に進みたくなる気持ちはわかりますが、まずは、止めてまで隣でアドヴァイス演奏をしている先生の音と言葉をよく聴く姿勢が必要でしょう。そこに上達のヒントが隠されています。
‣ 自分の話は指導者の話をきいてからする
前項目の内容に加えて、「言いたいことは、先生の話をきいてからにする」というのも大事だと考えています。
例えば先生が「ショパンがこの曲を作った頃は、彼がパリに移った直後で…」などと話し始めた時、「あーはい、それは○○で、それから…」などと話を横取りしてしまい、自分の言いたいことに変えてしまったりしていませんか。または、「私は、そういうのを○○だと思うので…」などと相手の話を遮ってまで自分自身に関する話へと変えてしまっていませんか。
筆者自身も注意しないとうっかりしてしまいがちなのですが、日頃我々はどうしても、人の話を聞いているフリをしながら「自分の話に持っていけそうな内容を、相手の話から探す」ということをしてしまいがちです。
先生と生徒のどちらが偉いわけでもありませんが、習いに行っている以上、まずは先生の話に耳を傾けて、それに対して反応したうえで、自分の言いたいことを切り出すようにしてみるのはどうでしょうか。
こういったやり方は、日常のコミュニケーションでも大事な部分ですね。よく、知識人同士が対談している動画を見かけますが、割と多くの動画でコミュニケーションが一方通行に感じます。それぞれの人が自分の言いたいことを言っているだけで、会話がキャッチボールになっていない。ただ気持ちよくなっているだけ。「分かります」「おっしゃる通りで」などと一言挟むだけで、即座に自分の話へ変えてしまう。結局、自分の話に持っていけそうな内容を、相手の話から探しているだけなのです。
適切なコミュニケーションは、指導者側にとっても生徒側にとっても成長のポイントとなるでしょう。
‣ 褒めてもらうことを目的にしない
自信を持つこと自体は大事なのですが、それがエスカレートして相手の意見を聞き入れない方向へいってしまうと、上達を邪魔します。
「これ以上直される部分はないから、褒めてくれ」
極論、これぐらいの意識でレッスンへ行く方もゼロではないでしょう。昔の筆者もそうでした。しかし、直される部分がないくらい学習していく心意気はOKですが、褒められることを目的にしてしまうのはNGだというのが、今現在の結論です。
この気持ちでレッスンへ行ってしまうと、指導者の意見を聞き入れないどころか、場合によっては、改善点を指摘された時にイラッとしてしまうことすらあります。大幅にテコ入れされることはもとより望んでおらず、「それでも、そこそこいいことを言ってくれたら、そこだけちょっと直そう」という気持ちになっている。
繰り返しますが、昔の筆者がそうでした。
最終的にどのように演奏を仕上げるかは自由です。しかし、まずは「素直になる」ということが必要だと考えています。「褒めてもらうことを目的にしない」ことを、習いにいくからには意識しましょう。
‣ はじめてのレッスンでも暗譜まで済んでいるところを目指す
新しい曲をはじめてレッスンへ持って行く時は、まだ上手く弾けない状態で、そういった部分をどう克服するのかもあわせて習いに行くのが普通になっているのではないでしょうか。
一週間で譜読みをして持って行くのにはある程度の限界があるのは確か。しかし、中級以上で、なおかつやる気のある方は、はじめてのレッスンでも暗譜まで済ませて持って行くことを目標に練習してみて下さい。
レッスンで弾く時に暗譜で弾く必要はありませんが、それくらいまで頑張ってあると、楽譜を見て弾く場合でも余裕度が全く異なります。演奏に余裕があると、レッスンで吸収できる量と内容が変わります。出来ている状態でのレッスンでは先生の指導内容も深さを増すでしょう。
「はじめてのレッスンまでに暗譜なんてムリ」と思っても、意外とそんなことはありません。選曲に関して意見をきいてもらえる先生に習っているのであれば、あらかじめコツコツ譜読みを進めておけばいいのです。
‣ なぜ、この前言われたことが出来ないのか
以前に、有名なバレリーナが芸能人にバレエを指導する番組を目にしました。意外とスパルタ指導で、「なぜ出来ないのですか?この前言ったでしょう。」などと、思いのほかキツく注意していたのです。
この注意は、ピアノの上達のためにもとても大事な観点だと思います。
習いに行っている方はもちろん、独学の方も動画や書籍で学んだり、時にはマスタークラスなどを受講や聴講することはあるでしょう。そんな時に、「一度言われたこと、一度学んだことを自分の中に残しておけるか」が進歩の分かれ目となってきます。
先人の言うことの全てが正しいとは限りませんが、少なくとも学習を積んできている方からの情報であれば、有益である可能性のほうが高いでしょう。
以前に言われたことが出来ない理由は、大きく以下の4点です:
・そもそも理解できなかったから
・面倒で習得しようという意識がなく、練習へ取り入れていないから
・練習へ取り入れていても、まだ実用レベルになっていないから
・先生のことを信頼できておらず、言うことを聞く気になれていないから
大事なのは、こういったところを楽しく乗り越えていこうと思えるくらいピアノに対しての熱意を持てるかどうか。以前に言われたことができるようになると、自分が成長するだけでなく、対人関係においては信頼までされるのです。
► B. 質問と学習の姿勢
‣ 指導者へ質問する「量」に注意する
「質問する量」として踏まえておくべきなのは、「質問をできる量は少なめに見積もっておくべき」ということです。
質問をたくさんすること自体はいいことです。自身で練習時間などを捻出している大人の学習者さんには熱心な方が多いでしょう。しかし、熱心なのは素晴らしいことなのですが、一度に何十個もの質問を書き出してきて責め立てるように質問をしてしまうのは問題と言わざるを得ないでしょう。
「説明して伝わったと思っても、実は2割くらいしか伝わっていなかった」ということは非常に多いので、一つの質問に対してより正確性を増して理解してもらうために具体例なども交えて解説すると、ある程度の時間がかかります。
ところが、熱心な方に限ってこちらの話をさえぎり強制的に終わらせて、次の質問をし始めがちなのです。「とりあえず、今自分が持っている疑問を表面的にでも全て解決しておきたい」という気持ちは分かります。さえぎり方には注意が必要で、強制終了だけは本当に気をつけましょう。
「質問のうちのいくつかはできない可能性がある」と思っておくことが必要です。いくつもききたいことがある場合は、質問順番(優先順位)を決めておくといいでしょう。
‣ 必ず、自分で考えてから質問する
中級者以上には注意して欲しい内容があります。それは、「表現を伴わない質問には、指導者も答えようがない」ことを踏まえて質問すべきということ。
例えば、「ここはペダルを使ってもいいですか?」という一言。ごく普通の質問だと感じると思います。この質問、初級者であればOK。本人もまだ何をどうしていいか分かっておらず、手取り足取り指導する必要があるからです。
しかし、中級者以上でこの質問をしてきた生徒には「何を表現したいのか」を考えてもらいます。
例えば、「軽さ」「ドライさ」などを表現したいのであれば、「それなら、ノンペダルのほうがいい」と答えるでしょうし、「ウェットさ」などを表現したいのであれば「それなら、ペダルを使ったほうがいい」などと答えるでしょう。そのうえで、指導者のほうで「和声」「声部処理」などを考慮し、テクニック的にどこでどれだけ踏めばいいかをあわせて指導します。
この「表現」がないと、答えなんて出ません。なぜなら、ペダルを踏んでも踏まなくても成立するところは山ほどあるからです。
とりあえず「ペダルを使ってね」などと言えば、あまり考えない学習者にとっては、指導者の言ったことが「唯一の正解」になってしまいます。次に同じようなところが出てきても考えることができない。
もちろん、ペダリングに限った話ではありません。解釈などに関するものであれば、ほとんどどれでも共通。
中級者以上になったのであれば、「自分で考えた結果、質問する」ことを始めてください。
少しきつい言い方になりますが、よく耳にする「何でもいいから、とにかくたくさん質問しよう」というアドバイスには耳を傾けるべきではないと思っています。自分で考えた結果、たくさんの質問がでてきたのであればOKです。しかしそうでない場合、教える側からみるとむしろ、楽して甘えているようにうつるのです。
この辺りは指導者の指導方針にもよりますが、将来の進歩のためにも筆者はこのようにしていくことを推奨します。
‣ レッスンなどで言われたことを自分に都合よく変換しない
音楽に関する会話を通して、自分の話した内容が相手の経験やボキャブラリーなどを通して都合よく変換されてしまうことは、結構多くあります。時には、自分が誤って解釈してしまっていることもあるかもしれません。
これを改善するには、話し手側が言葉の選び方に気を付けたり、聴き手側が早とちりしないように傾聴するしかありません。
例えば、何かの書籍の著者がある楽曲の一部のことを指して、「モーツァルトではペダルを薄めに」と言ったときに、「モーツァルトではどんな曲でもペダルを薄くしないといけないんだ」などと勝手に解釈してはいけません。このような聞き取り方をされていると感じることは本当に多いのですが、もう少し状況を考えて判断しないと安直なひとつ覚えになってしまいますし、上手くいかなかったときに相手のせいにしてしまいます。
習っている先生や、独学の方は各種教材などで、バンッと言われたことに対して今の知識で “真っ先に” 思い付く内容で処理をしないようにしましょう。そういった解釈の仕方をしていると、全て自分に都合のいい処理になってしまい、力がついていきません。
ボキャブラリー不足などに原因がある場合は、どうしようもないところもあります。ただし、「様々なことをもう少し慎重に眺める」ことを徹底すると、自分に都合よく変換する量を減らすことができて、結果的に、能力が上がったり対人関係がうまくいったりするでしょう。
► C. マナーと対人関係
‣ 週2回のピアノレッスンを検討しているケースの考え方
「週2回のピアノレッスンを受けてみたい、もしくは提案された」という方は少なくないはずです。
まず、週2回のレッスンを受けるケースを確認します:
・受講するのが子供で、集中できる時間が短いので2回に分ける
・取り組んでいる楽曲が多いので2回に分ける
・やる気があるので2回ともに全ての曲をレッスンしてもらう
・ピアノ教室でしか生のピアノを弾ける環境が無いため2回に増やす
・遠方から通っているので、2日に分けてまとめてレッスンしてもらう(受験生に多い)
・ダブルレッスンとして2名の異なる先生からレッスンを受ける(承諾は必須)
など。最後の2つは、やや特殊なケースですね。
当然ながら、レッスンを週2回にするとそれがどんな理由であれ、自分への負荷は上がります。自分の中で「練習スケジュール」や「譜読みをするタイミング」などの変化が起こります。習慣を変えざるを得ないのです。したがって、「一度週2回で相談してみて、自分の習慣の変化などが有効に働きそうなら続けていく」というのは一つの手だと言えるでしょう。
漠然と「週2回の方が上手くなりそうだから」という考えの場合は再考が必要です。先生との関係に新鮮味を保つことも大切なので、特定の理由がないのに回数だけ増やすと、かえってモチベーション的にはマイナスになることもあり得るのです。こういったある意味でのリスクを知っていても、きちんとした意図があれば回数変更を選択肢に入れるべきでしょう。
毎週のスケジュールに予約を作るわけなので、お互いに一種の拘束ができるということも忘れずに。「やっぱり辞めた」というのは先生のスケジュールを混乱させてしまうことになります。決意を持ってはじめて、どうしても難しいと感じたら、きちんと理由をお伝えして週1に戻して頂く。この部分がしっかりできるようであれば、相談してみるのはアリでしょう。
‣ レッスン時間内で熱心さを見せ、時間外で見せない
熱心なことは重要で、その熱意を指導者へぶつけることで指導者も応えてくれることでしょう。しかし、この熱意は原則「レッスン時間内でぶつける」ことを前提としましょう。時間外で見せようとすると、熱心さと相手への迷惑のバランスが取れなくなります。
時間内でも時間外でも熱心な方はいますが、時々、時間内では何もやらないのに、時間外では色々とお願いしている方もいるようです。どういうことかというと、本来の確保時間以外で何かをやることで、やった気になっているのです。これでは本末転倒と言わざるを得ません。
指導者との適切な関係性を保つために:
・レッスン時間外の対応は特別なサービスとして認識する
・たとえ普段の人間関係が良好でも、時間外のメールの返信を当然のことと思わない
・質問は可能な限りレッスン時間内 “のみ” で行う
・本来のレッスン時間が終わっているのに、自分の時間だと思って立て続けに質問しない
日頃お世話になっている指導者やオンライン上で繋がっている演奏家の方々に対して、レッスン時間以外でもメッセージによるアドバイスをもらいたい場面は出てくるものです。このこと自体は特に問題があるわけではありませんが、突然長文の質問や演奏データ、楽譜ファイルなどを一方的に送信するのは控えるべきです。
お願いをする際には手順というものがあり、いきなり大量の資料をガーンと送信するのではなく、まず最初に時間外での対応が可能かどうか、そして資料の送信許可をとることから始めないといけません。たとえ丁寧な文面でお願いしていても、突然資料を送りつける行為自体がマナー違反となります。
さらに、許可をいただけた場合であっても、演奏データや楽譜を複数送って「どちらでも構いません!」と記載するのは適切ではありません。「どちらでも構わない、どちらがよい」という表現は「どちらがよろしいでしょうか?」と尋ねられた際の返答であり、自発的に使用すると身勝手な印象を与えてしまいます。自分からお願いする立場で勝手に選択肢を提示するのは避けましょう。筆者も高校時代には悪意なく何度も同様の失敗を重ねていました。また、特別な取り決めがない場合は基本的に1回のお願いにつき1曲が原則です。
多くの場合、お願いされる側も可能な範囲でサポートしたいと考えているはずです。依頼の際は必ず段階的なアプローチを心がけ、自己中心的だと受け取られないよう注意を払いましょう。
‣ 大人だからこそやってしまいがちな教室マナー違反 3選
· 1. 大事なことは間接的に報告しない
知人の話をきいていると、以下のような会話は時々飛び交うようです。
生徒「その前に、コンクールの入賞者演奏会があるので」
指導者「何それ?」
生徒「あっ、この前受けたので」
こういう大事なことは、別の話題に挟んで間接的に報告したり突っ込んでもらうのを待っているのではなく、自分から報告しなくてはいけません。
コンクールを受けるかどうかは自由ですが、その先生に習っている以上、エントリーシートに師事者名を書くこともありますし、仮にそうでなかったとしても “事前に” 話を通しておくのがマナーです。
また、以下のような例も耳にしたことがあります。
などと生徒からメールが送られてきて、その後、音信不通になる。「習いにいこうとした当初の目標達成です。」ではなく、
というところまで、勇気を出して言わなければいけません。
という項目でも書いたように、「辞めさせてください」と言い出すことに一定のハードルがあることは分かります。しかし、こういう大事なことを遠回しに伝えるのはいけません。間接的に「辞める」ということを伝えて、その後音信不通になるのは、たとえ令和の時代でもマナー違反です。
· 2. 大事な報告を、電話や、ましてやメールに逃げない
前項で書いたようなことを直接伝えるのであればいいのですが、やり方としては、原則「対面」で伝えるべきでしょう。
「大事なことを電話で言ってはいけない」
筆者は以前、このように注意されたことがあり、今ではその価値観をもっています。ましてや、メールに逃げるのはNGです。
言い出しにくいのは分かりますが、「始める」というのは「いつか辞める時がくる」ということでもあり、始めると決めたからには、こういった大人としてのマナーは守らなければいけません。
· 3. 伏せている情報には触れない
先生のプロフィールをよく読んでみましょう。そこに書かれていない話題には、原則触れないのがマナーです。
例えば、生年月日が書かれていないのであれば、「ちなみに、おいくつですか?」などときいてはいけません。学歴が書かれていないのであれば、「ちなみに、どこの出ですか?」などときいてはいけません。その他諸々。
あらゆることを知ったうえで習いたいのであれば、はじめからそういうことを公表している先生を探せばいいのです。
► 終わりに
ピアノレッスンは、音楽的な理解を深め、独学では気づきにくい部分を磨く貴重な機会です。本記事で紹介した基本姿勢や質問の仕方、マナーは、より充実したレッスン体験へと導くヒントとなるでしょう。
関連内容として、以下の記事も参考にしてください。
【ピアノ】先生の選び方・正しい門のくぐり方・その後の付き合い方
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
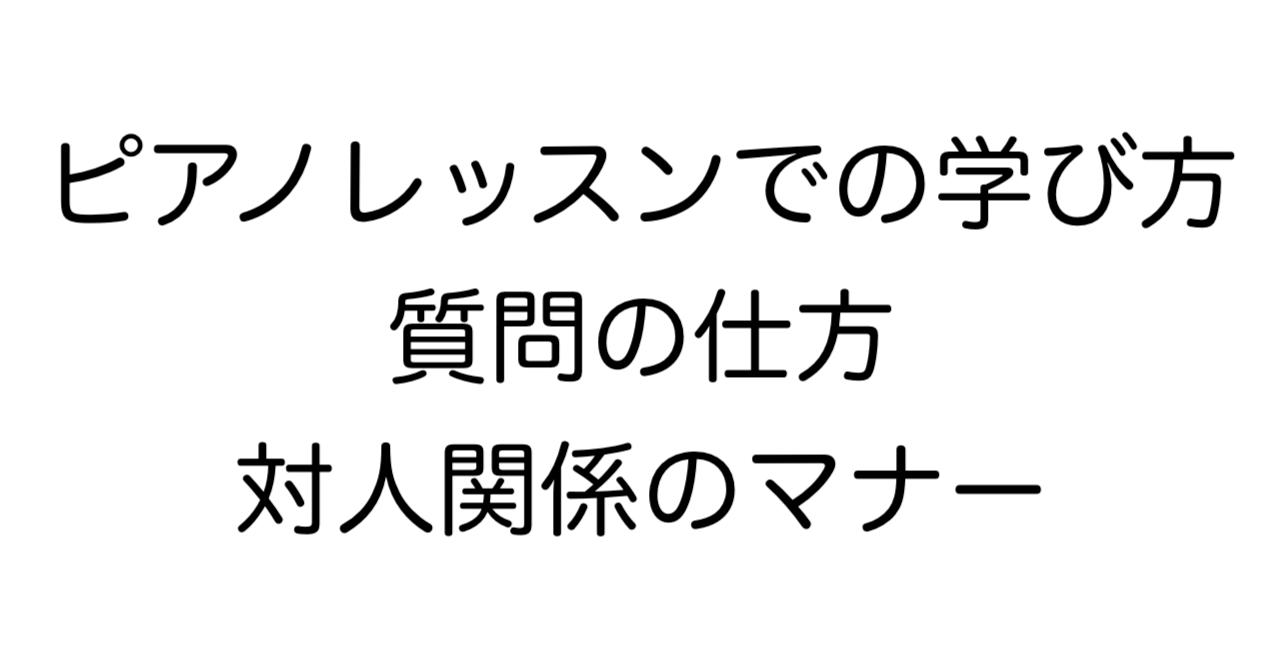
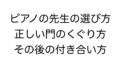
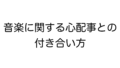
コメント