【ピアノ】繰り返しにおける些細な変化への徹底的な対応方法
► はじめに:繰り返しにおける細かな違いをすべて洗い出す
楽曲の中には、素材の大小はあれど繰り返しが出てくるものです。作曲家は、繰り返しの中にあるわずかな変化を通じて、音楽的な発展や様々な表現を実現しています。
一方、そのような繰り返しにおける細かな違いというのは、ときに演奏時の悩みの種になっていることでしょう。
心がけるべきなのは、譜読みをする段階から「どこが同じで、どこが異なるのか」といったことを、すべて洗い出しておくこと。そして、マーキングするに限ります。
こういったことを考えなくても、楽譜を見ているうちは弾けてしまいますが、しっかりと把握して考えておくことで以下のような利点があります:
・違いを区別しておくと、暗譜対策になる
・違いを弾き分けることで、表現そのものが変わる
・なぜそのような違いがつくられたのかを想像することで、楽曲理解のヒントになる
► 繰り返しなのに変化しているアーティキュレーション
特にドビュッシーなどの「こだわりが強く、まったく同じやり方による繰り返しを嫌う作曲家」に多いのですが、同じような音型の繰り返し時に、少しだけアーティキュレーションを変えていることがあります。
「暗譜しにくいので、どちらかに統一してしまってもいいかも」と思うかもしれませんが、答えはNoです。少なくともクラシック作品においては。
確かに、どれかに統一してしまった方が暗譜はしやすいですし、演奏自体も楽になります。しかし、それでは音楽が平坦になってしまうでしょう。作曲家が「それぞれ書き分けた」のは「それぞれ弾き分けて欲しい」ということです。
少なくとも音楽学をはじめとした研究者が研究し尽くしてきたクラシック作品の分野では、演奏しやすさを理由に楽譜に書かれているアーティキュレーションを変更するのは、原則避けておくようにしましょう。
► 実践的考察
‣ 実践的考察①:ソナタ形式の再現部における反れ始めポイント
ソナタ形式における再現部は、提示部と「同じ」または「似ている」状態で始まる場合が多いですが、再現部ではいずれ「違う方向」にそれ始めるので、そのポイントをよく理解しておくようにしましょう。
ベートーヴェン「ピアノソナタ 第18番 変ホ長調 Op.31-3 第1楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

「再現部の167小節目」に注意(譜例右)。うっかり手癖で「提示部の31小節目」(譜例左)と同じように弾いてしまうと、提示部に戻ってしまいます。矢印で示した箇所が、「違う方向」にそれ始めるポイントです。
こういう部分は身体で覚えるだけではなく、頭で整理しておいたうえで意識して演奏しないと、クセで間違えてしまう恐れがあります。ここで提示部に戻ってしまったら、「弾き直す」か「素知らぬフリをして提示部からまた弾く」しかなくなってしまうでしょう。
‣ 実践的考察②:変奏形式における微妙な変化
モーツァルト「ピアノソナタ ハ短調 K.457 第2楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-21小節)
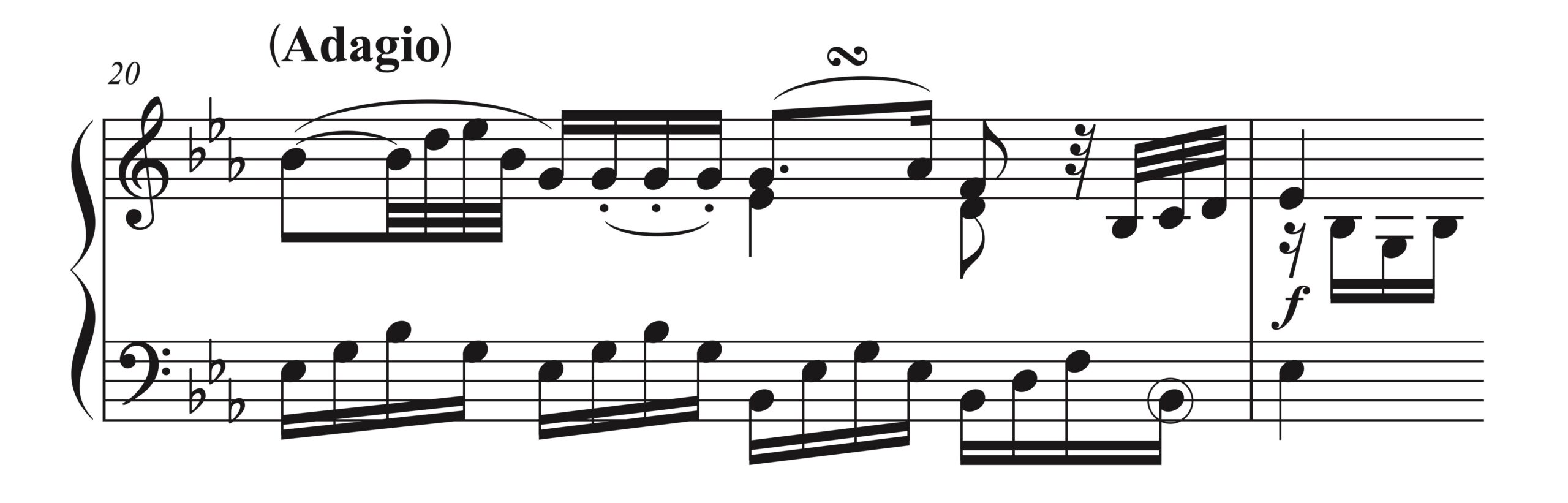
この楽章はロンド形式ということもあり、1小節目と同じ形が他に5回(同じセクションが計3回)も出てくるのですが、それぞれ、右手で弾く内容は変奏されて変化しています。
左手で弾く内容はまったく同じかと思いきや、4回目にあたる譜例の20小節目のみ、やや異なっています。他の回はすべて、譜例の丸印で示した音が長3度上のD音であることに注意しましょう。
いざ暗譜するとなったらどうすればいいのでしょうか。何回目が異なっているかというのは、暗記をすべきなのでしょうか。
少なくとも、この作品に限ってはその必要はありません。なぜかというと、メロディを見ると丸印をつけた音がD音ではなくB音に変えられた理由が明らかだからです。
(再掲)
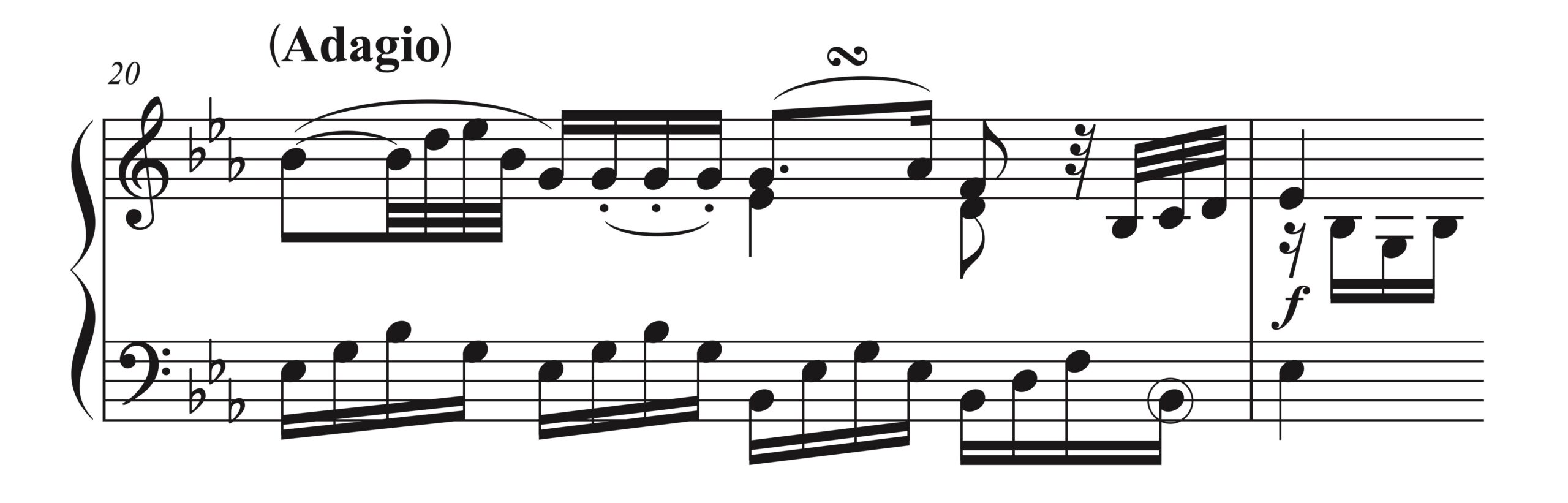
この楽曲の主調はEs-durで、20小節4拍目はEs-durのⅤであり、21小節目でⅠになっています。
ⅤのところにとってのD音は導音にあたるのですが、譜例の20小節目の最後ではメロディにD音が来ています。左手にもD音が出てくると導音重複(和声学では禁則)で響きのバランスを欠いてしまうため、メロディを優先させて左手側のD音を避けたのでしょう。
譜例では20小節目のみを掲載していますが、他の5回はメロディが変奏されていて、丁度話題としている瞬間にはメロディにD音が出てこないので、左手側にD音を使って導音が欠けないようにしたと考えられます。
‣ 実践的考察③:似ているけれども根本的な音の使い方が異なるもの
「似ているけれども根本的な音の使い方が異なる」といった部分も把握しておきましょう。
例えば、以下のようなもの。
モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第2楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成、28小節目 および 83小節目)
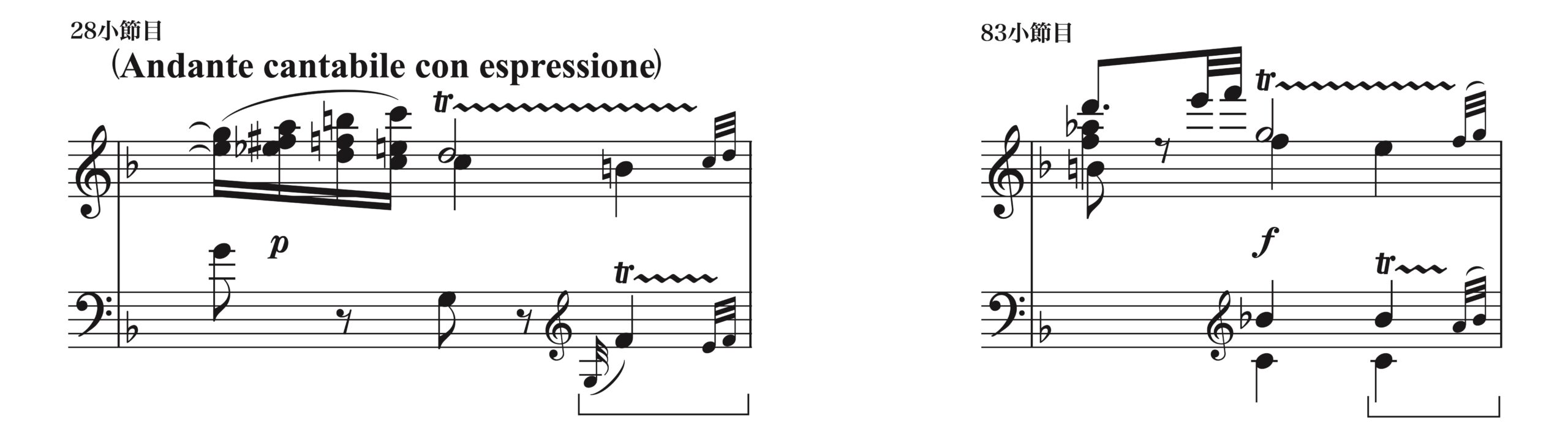
譜例は、提示部と再現部における対応する部分ですが、メロディそのものにも変化がありますし、その他の細かな違いは多くあります。
「似ているけれども根本的な音の使い方が異なる」という視点では、カギマークで示した部分に注目すべきでしょう。バスが小音符で書かれている書法とそうでない書法が、わざわざ使い分けられています。
► より深い比較分析
シューベルト「ピアノソナタ 第7番 変ホ長調 D 568 第4楽章」
譜例(PD楽曲、Finaleで作成)
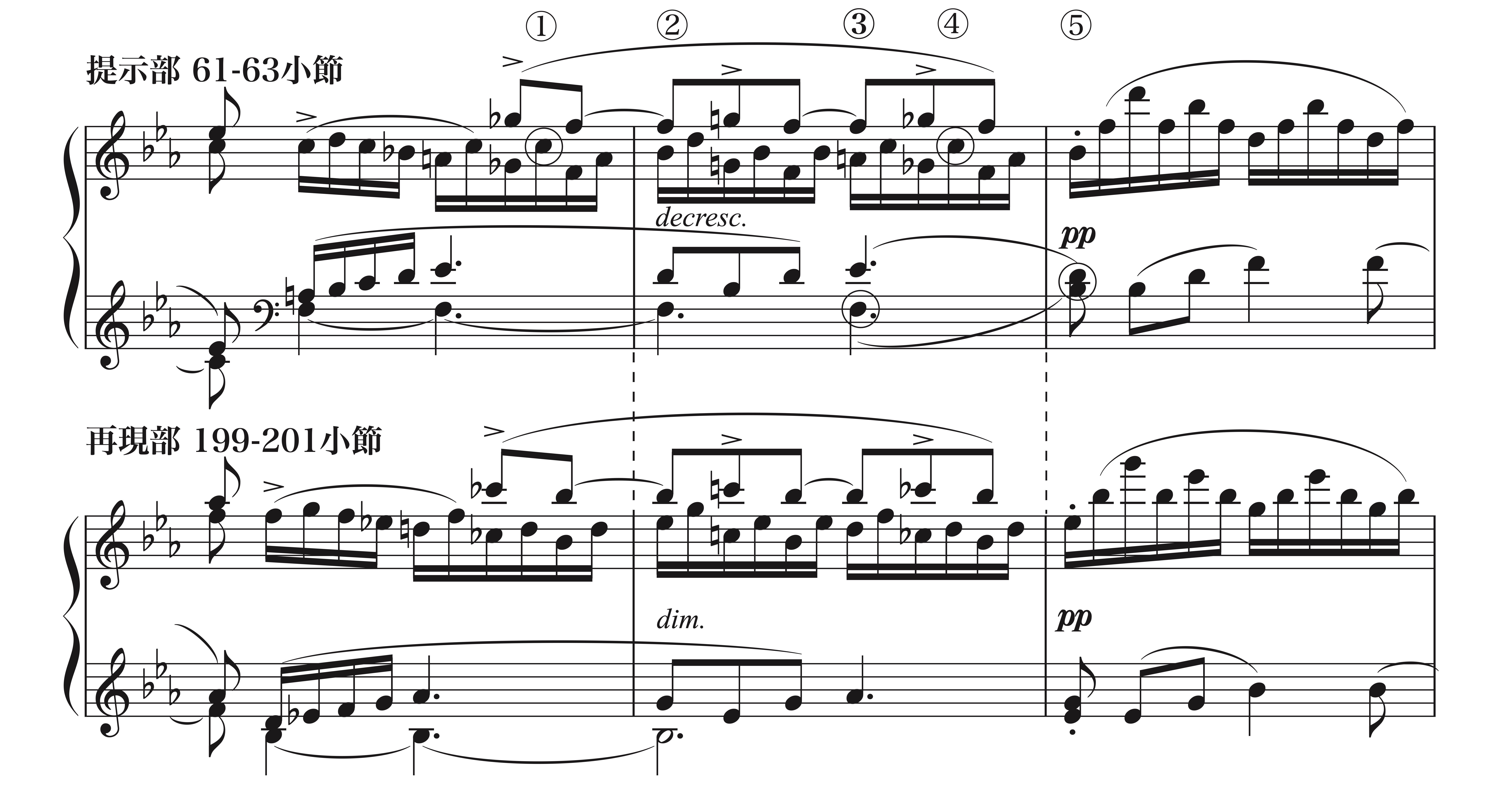
提示部の61-63小節ではB-dur(この楽曲における属調)で出てきている内容が、再現部の199-201小節ではEs-dur(この楽曲における主調)で出てきています。
ただ単に移調されただけではありません。スラーのかかり方に違いはありますが、それ以外にも五つの違いが見られます。
(再掲)
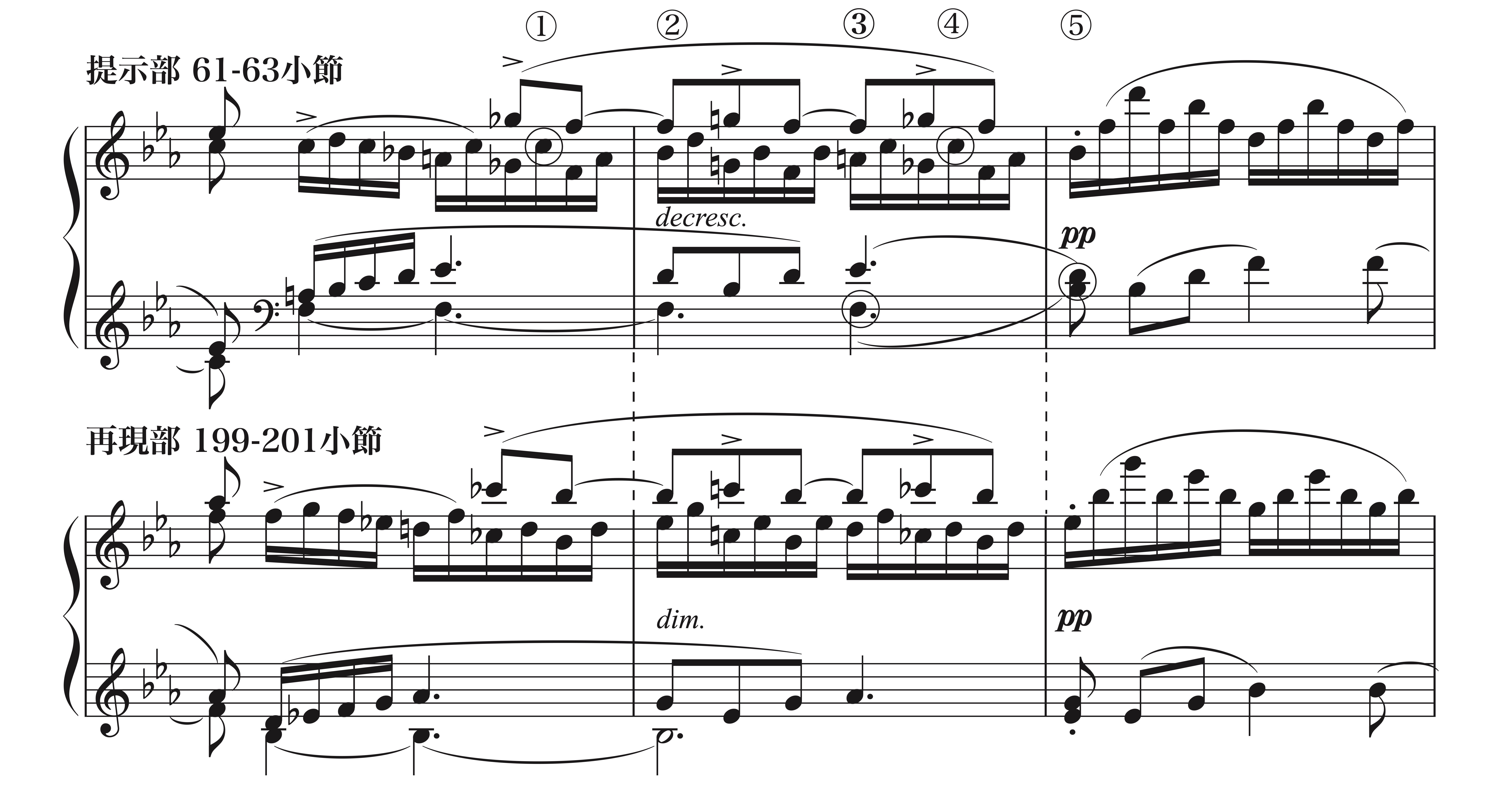
譜例に書き込んだ各番号について:
① 丸印で示した提示部のC音が、再現部ではF音ではなく3度下のD音になっている
② 提示部ではdecresc.が書かれているが、再現部ではdim.
③ 提示部ではバス音を付点4分音符で打ち直しているが、再現部では付点2分音符の伸ばし
④ ここは①と同様
⑤ 提示部では下段の和音にスタッカートが書かれていないが、再現部では書かれている
譜例は原典版を元にしていますが、これらの相違点は一つの版に依存したものではありません。
以下のように整理して考えてみてください:
①③④:
音の違いとして明らかに書き分けられているものなので、確実に弾き分けましょう。
②:
必ずしもすべての作曲家がdecresc.とdim.を一つの楽曲中で使い分けるわけではありませんが、シューベルトのdim.では「テンポをゆるめる」という意味もあわせ持っているとする考え方があります。細かく表現するのであれば「だんだん弱く」に加えてテンポ変化も考慮していいでしょう。
⑤:
提示部のほうにもスタッカートがついたからといって、音楽そのものに①〜④のような大きな影響はありませんが、
作曲家の意図的な書き分けだと判断して、一応弾き分けておくべきでしょう。
► 終わりに
楽譜に書かれた繰り返しの違いを理解することは、機械的な作業ではありません。作曲家の意図を理解し、より深い音楽表現を実現するため、そして、演奏に活かすための重要な第一歩となります。
実践への応用:
・新しい楽曲に取り組む際は、必ず繰り返し部分の比較をする
・違いを見つけたら、その音楽的な意味を考える
・理解を踏まえたうえで、丁寧に弾き分ける
・暗譜の際は、違いを整理して理解することで、より確実な記憶につなげる
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
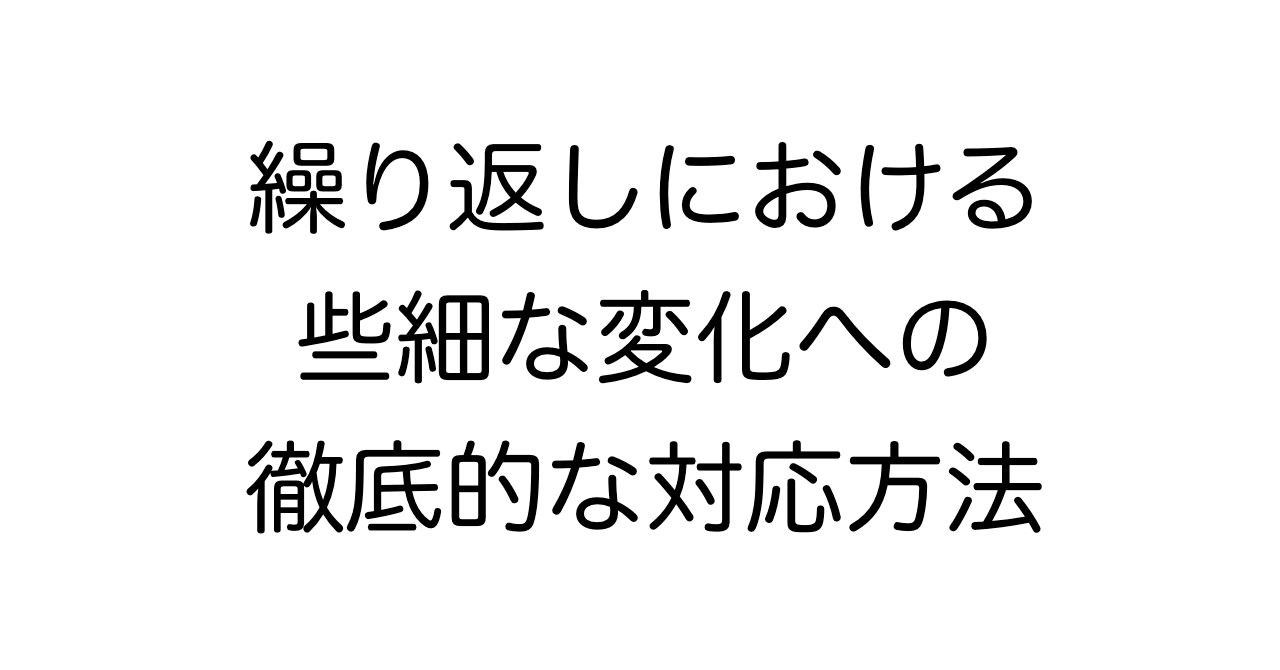
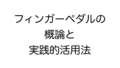
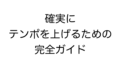
コメント