【ピアノ】映画「ラフマニノフ ある愛の調べ」レビュー
► はじめに
セルゲイ・ラフマニノフを描いた映画「ラフマニノフ ある愛の調べ(Ветка сирени)」を紹介します。この作品は、ピアノ音楽の素晴らしさや、創作の苦悩、そして音楽家としての生き方を描き出した映画です。
本記事では、ピアノ的視点から、この映画の魅力と特に注目すべき楽曲の使われ方について詳しく解説します。
・公開年:2007年(ロシア)/ 2008年(日本)
・監督:パーヴェル・ルンギン
・ピアノ関連度:★★★★★
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はお気をつけください。
‣ ピアノ演奏シーンの見どころ
本映画では、ラフマニノフ本人によるピアノ演奏シーンの数々が出てきます。
ラフマニノフは作曲家としてはもちろん、自身の作品や他者の作品を演奏するピアニストとしても知られていました。それを、自作品に加えてショパンやスクリャービンを弾くシーンも含めることで示しています。ちなみに、演奏シーンはもちろん、「ピアノ協奏曲 第2番 Op.18」を作曲するシーンや教育活動をするシーンも含まれ、音楽家としての活動を幅広く描いています。
また、演奏シーンが単に「美しい音楽を聴かせる場面」ではなく、以下のような具体的な作品を通じて、ラフマニノフの内面や人間関係、創作の苦悩を映し出す重要な役割を果たしている点も特徴的です。
‣ 作品に登場するラフマニノフのピアノ曲
ラフマニノフの代表作から隠れた名曲まで、様々なピアノ曲が効果的に使用されています。
代表的な登場曲:
・ピアノ協奏曲 第2番 Op.18:映画の中でラフマニノフが作曲する過程も描かれる、本映画の軸となる作品
・パガニーニの主題による狂詩曲 より 第18変奏:特にラストシーンで使用され、感動を誘う
・ヴォカリーズ
・幻想小品集 Op.3-1 エレジー
・幻想小品集 Op.3-2 前奏曲
・前奏曲集(プレリュード) 第12番 Op.32-12
‣ 音楽の使われ方から見る映画の特徴
この映画の音楽演出で注目すべきなのは、「状況内音楽」と「状況外音楽」の使い分けです。
状況内音楽とは:
・ストーリーの中で実際に聴こえている音楽
・登場人物がピアノを弾いているシーンのBGMなど
本映画における状況内音楽:
劇中でオーケストラが演奏するシーンやラフマニノフ自身がピアノを弾く場面で使用される音楽。彼が実際に演奏するシーンでは、作曲家としてだけでなくピアニストとしての側面も強調されています。
本映画における状況外音楽:
物語の背景として流れるBGM。終盤までは、意図的にピアノサウンドが控えられています。
この対比が最も印象的なのがラストシーンです。それまで「状況内音楽」として実際の演奏シーンで聴かれていたピアノサウンドが、ラストでついに「状況外音楽(BGM)」として全面に押し出されます。「パガニーニの主題による狂詩曲 より 第18変奏」が流れる瞬間は、まさに映画のクライマックスとして心に残ります。
‣ 音楽史的視点から見た留意点
詳細は映画本編で確認して欲しいのですが、本映画の内容は、有力とされているラフマニノフの音楽史の内容と異なる点もあります。あくまで映画として楽しむことを重視しましょう。
► 終わりに
「ラフマニノフ ある愛の調べ」は、音楽の原点となる「感情」や「人生経験」の重要性を教えてくれます。上記のような音楽使用面での工夫も意識しながら、「一度」もしくは「もう一度」鑑賞してみてください。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
・お問い合わせ
お問い合わせはこちら

![ラフマニノフ ある愛の調べ [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/41qaHoGSNuL._SL160_.jpg)
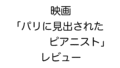
コメント