【ピアノ】武満徹のショパン論(1960年):魅了と批判の狭間で
► はじめに
1960年、30歳の武満徹が『レコード芸術』誌に寄稿した「たった一人のショパン 作曲家のショパン観」は、作曲家の視点から見たショパン論として、興味深い内容となっています。この時期の武満は、1960年代後半に迎える芸術的頂点の直前にあり、前衛作曲家としての思想が最も先鋭化しつつある時期でした。その武満が、ロマン派の巨匠ショパンをどう見ていたのか——肯定と否定が交錯する、複雑な視点と感情がそこにあります。
参考文献:武満徹「たった一人のショパン 作曲家のショパン観」『レコード芸術』1960年1月号(『武満徹著作集5』新潮社 所収)
· 武満徹著作集〈5〉/ 新潮社
► 内容について
‣ 音楽ファンとしての武満:抗いがたい魅力
武満は率直に告白します。「一音楽ファンとして云えば、私はショパンは好きで、毎日のように弾いてみたりする」と。ショパンの音楽には「非常に魅惑的な魅力」があり、「みんなが好きだとか、嫌いだとか云えないような独特の美しさ」があると認めています。
実際、武満はショパンの技術的な卓越性も高く評価していました。大胆なハーモニー、遠隔調への転調など、当時としては目を見張るほどの技術があったこと。そして何より、ピアノという楽器の可能性を驚くほど拡げた功績を讃えています。「ベートーヴェンやシューベルトに比べてピアノのしゃべり方を驚くほどに拡げている」「曲として優れた書き方は、すでにショパンに典型がある」——ショパン以後、ピアニスティックな意味で独特なのはドビュッシーとバルトークくらいで、あの楽器を十分に活かしている作曲家として、武満はショパンを高く評価していたのです。
さらに武満は、ショパンの即興性にも注目していました。「ショパンの音楽にはたいへん即興的な面がある。それが音楽としてよくバランスしている、即興に破綻がない」と述べ、「ショパンの即興性というものには注目していいと思っています」と肯定的に語っています。これは当時の現代音楽が失いつつあった「その瞬間の感情や呼吸から自然に湧き上がる、生きた音楽性」を、ショパンが持っていたことへの評価でもありました。
‣ 作曲家としての武満:厳しい批判の眼差し
しかし、作曲家としての武満は全く異なる視点からショパンを見ています。その批判の核心は、ショパンが「音そのものを通じて思考する」のではなく「音によって夢みている」という点にありました。
武満は有名な「石鹸のたとえ」を用います。石鹸で大切なのは香料やデザインではなく、汚れをよく落とすこと。作曲家もまず「よく落ちる石鹸」を作らなければならない——つまり、音楽の伝統を歴史的に形作っていくという本質的な仕事をすべきだというのです。しかし「ショパンにはそういう意識が非常に希薄」だと武満は指摘します。
形式面での批判も鋭いものでした。右手の旋律に対する左手の伴奏の単純さ、ノクターンなどに見られる装飾的な変奏にとどまる主題展開の不在——「本質的な意味での主題の展開がない」という指摘は、前衛作曲家としての武満らしい視点です。
‣「たった一人のショパン」という孤高
武満の批判で最も本質的なのは、ショパンが「外部の現象に対して全人間的に傾斜したのではなく、単に感情だけで傾斜した」という点です。ポーランド革命に触発された作品もありますが、それは「個人的な感傷、単に感情傾斜にとどまってしまって、全人的な感動をもったのではない」と武満は見ています。
音楽家にとっての現実参加とは、政治的・社会的な主題を持ち込むことではなく、「音以外のなにものでもない」——つまり音という素材そのものと格闘することだというのが武満の持論でした。その意味で、ショパンの音楽は「あまりに即興的であって、われわれが抜き出す未来を形作る要素というのが非常に少ない」のです。
武満はショパンとドビュッシーを対比させます。ドビュッシーもショパン的な資質を持っていたが、「彼の技法というものは、いつでも現実、つまり音と一致していた」。一方、ショパンは「往々感覚のあざむきがちな働きかけに身を流してしまう」「意志的なものが乏しい」——この対比は、武満の音楽観を端的に示しています。
そして武満は、「ショパンという人間は非常に孤高にすぎた」と総括します。「なにか恋愛を愛してしまったように、作曲をも夢見ているようなところがあった」という逆説的な表現で、ショパンの芸術的姿勢を批判的に捉えています。ロマン派の作曲家たちは「すべてピアノを中心に動いている」——自分が直接演奏できる楽器との個人的・情緒的な関係が、深い精神的な次元での人間的な創造を妨げたのではないか、と。
‣「たった一人のショパン」というタイトルの意味
この文章のタイトル「たった一人のショパン」には、二重の意味が込められています。一つは、ショパンの独自性・唯一性への賞賛。もう一つは、後続の作曲家たちに継承されるべき要素を十分に残せなかった孤立性への批判です。
「外部の現象に対して情緒的な傾斜にとどまってしまったというような点」が、「ショパンをたった一人のショパンにしてしまった」——この繰り返される結論に、武満の複雑な思いが凝縮されています。
► 終わりに
1960年の武満徹によるこのショパン論は、当時の前衛作曲家としての理念と、一人の音楽愛好家としての感性が交錯する、誠実な文章です。30歳の武満が抱いていた、音楽は「音そのもの」を通じて現実に参加すべきだという信念が、ショパンへの両義的な評価を生み出しました。
皮肉なことに、後年の武満は、若き日の自分が批判した「夢見るような美しさ」といった要素を、自らの音楽に取り込んでいくことになります(特に1980年代以降)。この1960年のテキストは、武満徹という作曲家の思想的変遷を考えるうえでも、貴重な資料と言えるでしょう。
参考文献:武満徹「たった一人のショパン 作曲家のショパン観」『レコード芸術』1960年1月号(『武満徹著作集5』新潮社 所収)
· 武満徹著作集〈5〉/ 新潮社
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
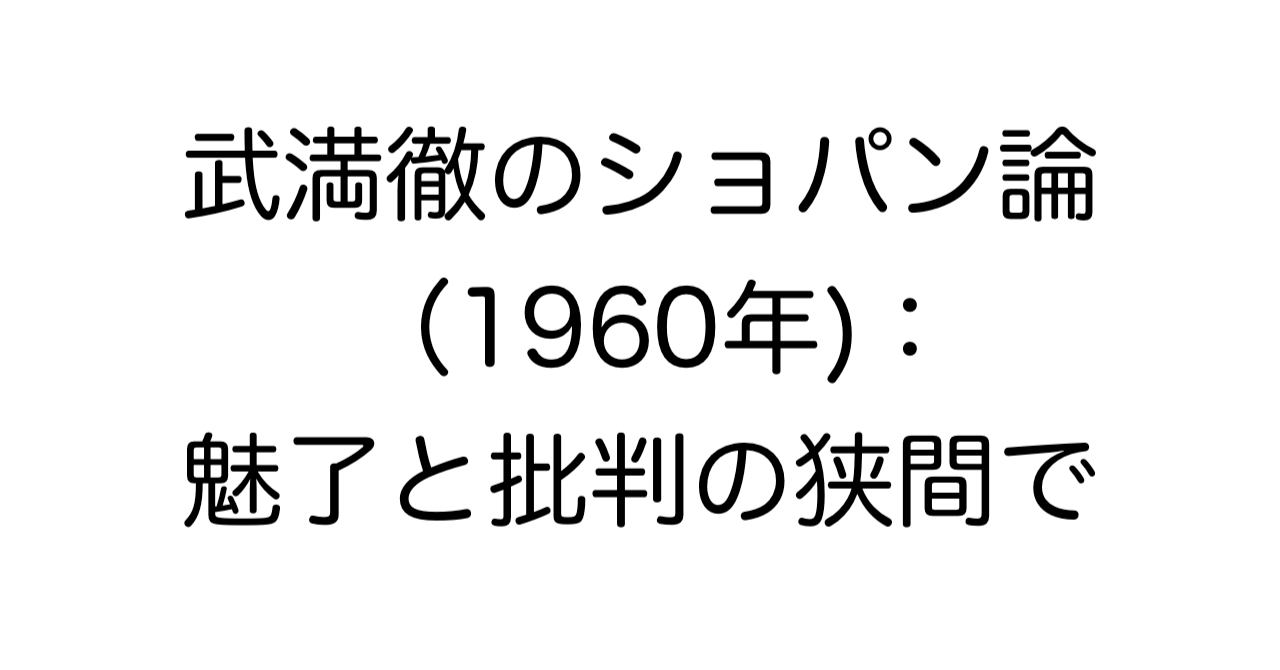


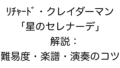
コメント