- 【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.19
- ► はじめに
- ► 質問集
- ‣ Q1. 疲れている日は、練習を休むか、簡単な曲だけ弾くか、どちらがいい?
- ‣ Q2. 練習中に動画サイトの「お手本演奏」を聴き過ぎるのは、自分の音楽性を失う?
- ‣ Q3. 譜読みの段階で、いきなり両手で弾くのは非効率的?
- ‣ Q4. 指の力が弱いのを、ピアノ以外のトレーニングで補うべき?
- ‣ Q5. ピアノを弾くとき、指輪や時計は外すべき?
- ‣ Q6. 自分で購入した楽譜に、先生の許可なく勝手に書き込んでもいい?
- ‣ Q7. 楽譜に書き込んだ内容が多過ぎて、楽譜が読みにくくなってしまった
- ‣ Q8. 練習環境としてグランドピアノのあるスタジオを借りるのは、どのようなメリットがある?
- ‣ Q9. 先生から推薦された「難しい音楽書籍」とはどう付き合う?
- ‣ Q10. 音楽用語の日本語訳が多過ぎて混乱する。どれを覚えればいい?
- ► 終わりに
【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.19
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. 疲れている日は、練習を休むか、簡単な曲だけ弾くか、どちらがいい?
結論:少しでも練習し、習慣を維持する
学習では習慣づけとその維持が最も重要です。たとえ15分のみでも、ピアノの前に座ることをおすすめします。
完全に休む日を曜日固定で設けているのであれば問題ありませんが、そうでない場合、不意に休むと習慣が乱れて、次に始めるときにかえって辛くなります。疲れていて長時間は集中できないと思うので、わずかな時間で構いません。
実際のところ、誰でも完全に疲れていない日などほとんどありません。「今日は休もう」という姿勢が「今日も休もう」につながってしまうのです。
‣ Q2. 練習中に動画サイトの「お手本演奏」を聴き過ぎるのは、自分の音楽性を失う?
結論:気にせずたくさんの音楽を聴くべき
譜読みを始める前に聴き過ぎたり、極端に癖の強い演奏ばかりを参考にするのであれば、学習的にマイナスになることもゼロではありません。しかし基本的には、聴いただけで影響を受けるほど演奏を深く理解することは容易ではありません。
例えば、ポリーニの素晴らしいショパンのエチュード集を繰り返し聴けば、演奏は変わるのでしょうか。おそらく、ピアノに向かうと演奏はいつも通りになるはずです。
あまり色々考えて聴く音楽が四畳半になるよりも、臆せずどんどん聴いていきましょう。
‣ Q3. 譜読みの段階で、いきなり両手で弾くのは非効率的?
結論:作品のタイプによって戦略を変える
筆者自身のやり方でもあるのですが、譜読み初期のやり方として、以下のプロセスが効率的です:
・片手ずつ運指を決めていく
・両手で組み合わせて一つのパッセージを作っている部分は、両手で運指を決める
・運指が決まったら、早速両手で合わせていく
・極端に難しい部分は片手で集中的に練習する
楽曲は基本的に両手で一つの音楽を作っていくものです。入門段階が終わってある程度ピアノ演奏に慣れてきたら、運指決定後は両手で譜読みをしていくことをおすすめします。
別のアプローチが必要な場合
一方、ロシア作品の一部(ラフマニノフ、プロコフィエフ など)は、ゆっくりしたテンポでは音楽の姿が見えにくい構造を持っています。こうした楽曲では、各手が十分な速度で動けるようになってから合わせないと、「これで合っているのか?」という混乱が生じます。
このタイプには:「片手を個別に仕上げる → ある程度の速度で弾けるようになってから統合 → ゆっくり合わせる」
要するに、「両手譜読み」自体に良し悪しはなく、作品が要求する音楽的理解の方法に応じて柔軟に対応することが鍵となります。
‣ Q4. 指の力が弱いのを、ピアノ以外のトレーニングで補うべき?
結論:原則不要。やるとしても体系化されたものを
小学生が細い指で達者な演奏をするのを聴いても、筋力をつけるとピアノが上達すると思えるでしょうか。
ピアノを弾くときに必要な最低限の筋力、大きく響く音を出すための身体の使い方、音を出すタイミング、頭の混乱の解消と指の動きの関連——こういったことはすべて、ピアノの練習の中で習得するしかありません。
バネで指を鍛えたりする必要はなく、シューマンのように怪我をしないことのほうが大切です。
もしどうしても何かを取り入れたいのであれば、「ミキモトメソッド フィンガートレーニング」のように体系化されていて、専門の指導者もいる分野を検討するほうがいいでしょう。筆者自身もレッスンを受けていた時期があります。
指を速く動かすことに問題を感じているのであれば、むしろ「頭を混乱させる練習」を取り入れることをおすすめします。詳しくは、【ピアノ】指を速く動かすための混乱学習法 という記事をご覧ください。
‣ Q5. ピアノを弾くとき、指輪や時計は外すべき?
結論:このような判断はすべて、本番を想定すべき
本番でピアノを弾くとき、ほとんどの方は指輪や時計を外すはずです。このような判断はすべて、「本番ではどうするか」ということを想定するようにしましょう。
本番にあらゆる状態を近づけて日頃から積み上げるのがポイントです。
‣ Q6. 自分で購入した楽譜に、先生の許可なく勝手に書き込んでもいい?
結論:学習に必要な内容であれば、構わない
自分で購入したものであれば、書き込むこと自体は問題ありません。運指をはじめ、書いておくと学習が捗る内容はむしろ積極的に書き込みましょう。
基本的に、よほど変わった先生でなければ怒ることはないはずです。ただし一例として、楽譜へ書き込みを多くしていたら「他の先生にも内緒で習っているの?」と疑われたという話を耳にしたことはあります。
‣ Q7. 楽譜に書き込んだ内容が多過ぎて、楽譜が読みにくくなってしまった
結論:書き込みもテクニック。自分にとって必要な内容を選択する視点を持つ
書き込みは積極的に活用すべきですが、楽譜を真っ黒にしてやった感を得たからといって、それで上達するわけではありません。自分にとって必要な内容を選べるよう意識しましょう。
読みやすい楽譜にするための書き込みのコツ:
・すべての書き込みは見やすい大きさを意識し、大き過ぎもNG
・運指の書き込みは推奨
・音名の書き込みは入門段階が終わるまでに卒業する
・後ろ寄りのクレッシェンドなど、自分なりの記号化が可能な部分は、言葉よりも記号を積極的に活用する
・読み返してみて自明のことは、消すのも一案
推奨記事:【ピアノ】楽譜への書き込みの活用法と、作曲家の書き込みの解釈法
‣ Q8. 練習環境としてグランドピアノのあるスタジオを借りるのは、どのようなメリットがある?
結論:以下の4つの主要なメリットがある
1. 集中力の向上
費用がかかっているうえ制限時間が決まっているため、練習に対する集中力が続きやすくなります。
2. モチベーションの維持
「周りの人も練習している」という事実が、自身のモチベーションを高めてくれます。
3. 本番対策と新鮮味
普段使用していないピアノに触れることで、本番での適応力を養えるうえ、練習に新鮮味を取り戻せます。
4. 時間の柔軟性
早朝対応可能なスタジオの場合、仕事などの都合で日中練習できない学習者にとっても有益です。
‣ Q9. 先生から推薦された「難しい音楽書籍」とはどう付き合う?
結論:完読を目指さず、使える部分から吸収する
指導者が推薦する専門書は、往々にして学習者のレベルより高度な内容を含んでいます。これは悪いことではなく、むしろ成長の余地を示しています。問題は、「最初から最後まで完璧に理解しなければ」という心理的プレッシャーです。
実践的な読書戦略
まず理解すべきは、音楽書の多くは辞書的な使い方ができるということ。通読する必要はなく、今の自分に関連する章や節だけを読むので十分です。
加えて、抽象的な音楽論は一度読んだだけで腑に落ちることは稀です。むしろ、「今はピンとこないが、いつか分かるかもしれない」という箇所にマークをつけておき、数ヶ月後に読み返すと驚くほど理解できることがあります。
翻訳書特有の工夫
外国語文献の翻訳では、訳註が巻末にまとめられていることがあります。これが読書の大きな障壁になります。対処法として:
・紙の書籍:思い切って訳註部分を裁断し、別冊化する
・電子書籍:タブレット等の別デバイスで訳註ページを常時表示
要するに、横へ置きっぱなしにしておけばいいのです。こうすることで、本文と註をシームレスに行き来でき、読書のストレスが大幅に軽減されます。
読書メモも有効です。ただし「要約」ではなく、「自分の言葉での解釈」や「疑問点」を記録することで、後日の復習や指導者への質問に活用できるようにしましょう。
‣ Q10. 音楽用語の日本語訳が多過ぎて混乱する。どれを覚えればいい?
結論:参照する辞書・資料を固定し、情報の一貫性を保つ
音楽用語の日本語訳は資料によって異なり、例えば「agitato」は「激しく」「いら立って」「興奮して」など複数の訳語が存在します。この多様性が学習の妨げになることがあります。
非効率な学習パターンの典型例
ある日、楽譜に「agitato」を見つけてウェブ検索し、「いら立って」という訳を知る。数週間後、別の曲で同じ用語に出会い、また検索すると今度は別サイトで「激しく」と書かれている。この繰り返しでは記憶が定着しません。
推奨される学習方法
重要なのは「情報源の統一」です。信頼できる音楽用語辞典を1冊選び、それを自分の「基準辞書」として使い続けることです。その辞書に載っていない用語があれば、補助として2冊目を用意しても構いませんが、最大でも2〜3冊に限定しましょう。こうすることで:
・同じ用語は常に同じ訳語で記憶される
・復習時も同じ説明に出会うため、知識が強化される
・学習内容に一貫性が生まれ、体系的理解につながる
その場限りの検索に頼る学習は、幅広いトピックの概要をつかむ際には有効ですが、音楽用語のような「積み重ねが必要な知識」には不向きです。むしろ、選んだ辞書をそばに置き、忘れたら何度でもその同じページを開く——この地道な反復こそが、確実な定着をもたらします。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
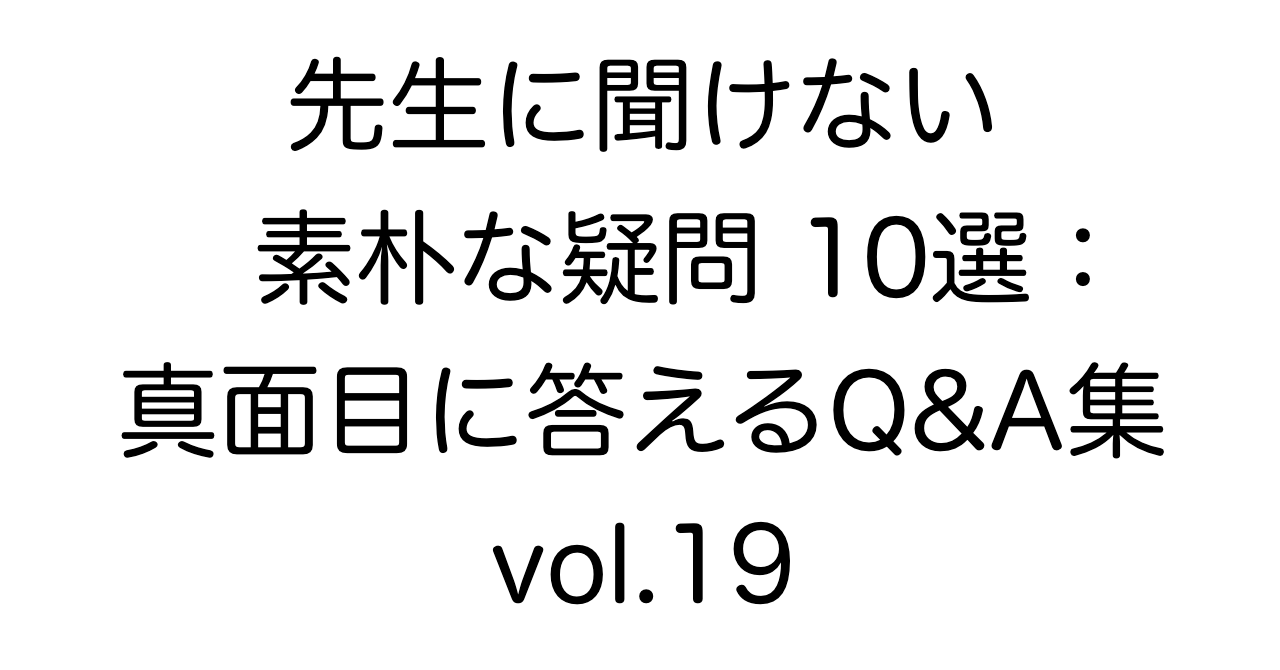
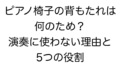
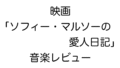
コメント