【ピアノ】映画「チャイコフスキー」レビュー:ピアノ音楽の演出分析
► はじめに
「チャイコフスキー(Чайковский)」は第一部と第二部に分かれた157分の大作であり、音楽的にも注目すべき点が数多くあります。本記事では、その中でもピアノ音楽に関連する部分を中心に解説していきます。
・公開年:1970年(ソビエト連邦)/ 1970年(日本)
・監督:イーゴリ・タランキン
・ピアノ関連度:★★☆☆☆
► 内容について(ネタバレあり)
以下では、映画の具体的なシーンや楽曲の使われ方について解説しています。未視聴の方はご注意ください。本記事では、曲名は一部俗称を用いています。
‣ 後から説明される状況内音楽
序盤、チャイコフスキーの背後でピアノや声楽の音楽が流れています。この時点では「状況内音楽」(ストーリー内で実際にその場で流れている音楽)の可能性が予想できるものの、演奏体が映し出されているわけではないため、まだ確証は得られません。
「先生、こんばんは」と言って通り過ぎるヴァイオリンを持った男性の存在により、音楽学校の中である可能性が高まります。そして後にようやく、ここがモスクワ音楽院の中であることが明かされるのです。
この演出は、観客に段階的に状況を理解させる効果的な状況内音楽の手法と言えるでしょう。
‣ 実際の作曲家像を反映したセリフのやり取り
ピアニストのニコライ・ルビンシテインが、チャイコフスキーの作品に対して「手の使い方が難しい、ピアニスト泣かせだ」と発言し、チャイコフスキーが「私はピアニストにではなく、聴衆のために書いている。演奏家の都合に合わせた手法はごめんだ」と返すシーンがあります。
この会話はただの創作ではなく、実際のチャイコフスキーのピアノ音楽に対してよく指摘される特徴を反映していると考えられます。チャイコフスキーのピアノ作品を演奏した経験がある方であれば感じたことがあるかもしれませんが、彼の音楽は美しい響きを持つ一方で、ピアノ奏法の観点から見ると弾きにくい箇所が比較的多いのが特徴です。
千蔵八郎氏も「ピアノ音楽史事典(春秋社)」の中で、以下のように述べています。
みずからピアニスト活動をしている作曲家の作品にみられるようなピアニズムが、彼のピアノ曲にはあまり感じられない(中略)彼のピアノ作品には「鍵盤に密着した書法」つまり「現場的感覚」が希薄である
(抜粋終わり)
‣ 皮肉としての状況内音楽
上記のニコライ・ルビンシテインとのやり取りの直後、別の部屋でルビンシテインはチャイコフスキーに聴こえるように、ベートーヴェンの「皇帝協奏曲 第3楽章」を演奏します。これは、「ピアノ協奏曲 第1番」を作曲中のチャイコフスキーに対する皮肉と受け取れます。そして「このように書くんだ」とルビンシテインが発言することで、その意図が明確になります。
チャイコフスキーが皇帝協奏曲の響きをかき消すかのように自分の協奏曲を力強く弾き、2種類の状況内音楽—それも2つの協奏曲による音楽—が場面を包み込みます。この演出は、両者の関係性を音楽的に表現した秀逸な場面と言えるでしょう。
ちなみに第一部の中盤、モスクワ音楽院の中で再び皇帝協奏曲が聴こえる場面があります。おそらく学生の練習風景でしょう。これもあえてこの作品を状況内音楽として選んだことに、先ほどのルビンシテインの皮肉の場面との関連を感じさせる演出効果があります。
‣ その他の注目すべきポイント
音楽ジャンルの対比効果:
飲食店で流れるノンクラシックのピアノ音楽が、クラシック音楽との対比効果を生み出している
歌曲のBGM使用:
状況外音楽(通常の外的に付けられたBGM)に歌曲を用いている箇所が新鮮
音楽そのものを楽しませる演出:
音楽をただのBGMとしてではなく、それを聴くことを目的とした場面が多く、音楽そのものを堪能できる
・ルビンシテインの死の場面では、ピアノ協奏曲第1番が長時間使われる
・マイヤ・プリセツカヤのバレエに合わせた「白鳥の湖」の使用
・ラストシーンにおける交響曲第6番「悲愴」の初演
► 終わりに
本映画では、特に第一部にピアノ関連のシーンが多く見られます。長編作品ではありますが、音楽の充実度とともに見応えがあり、過度な脚色もないため、価値ある一作としておすすめできます。
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
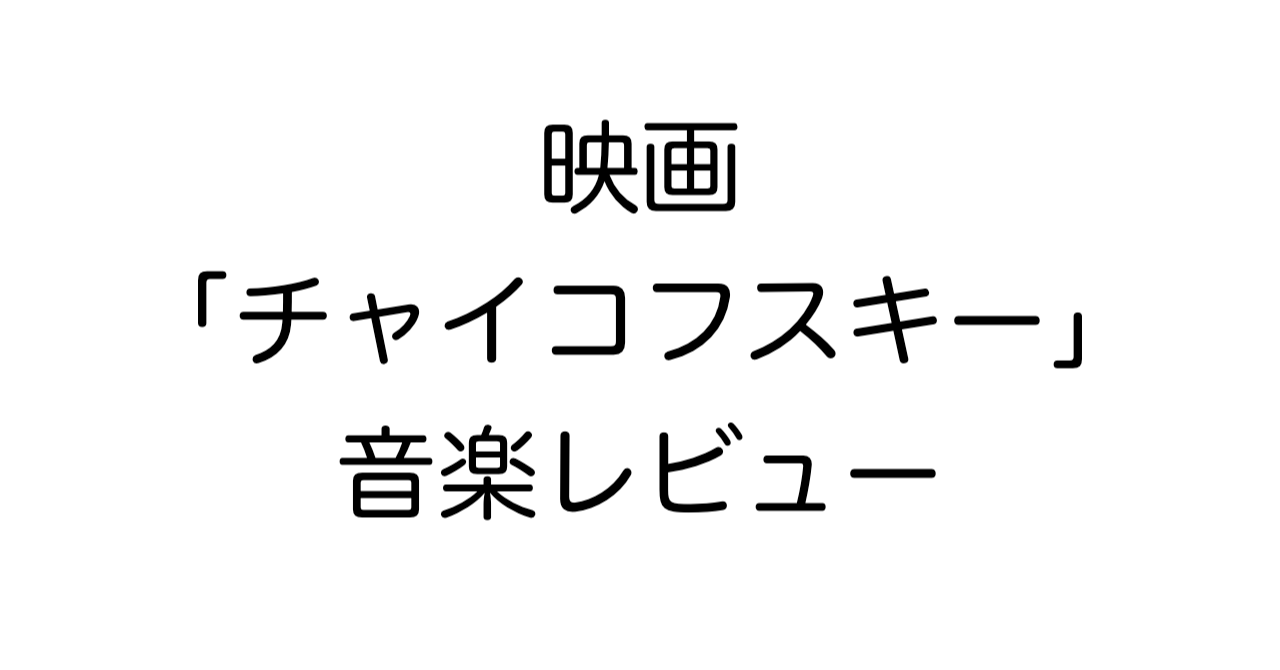
![チャイコフスキー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51l-Wnwm5SL._SL160_.jpg)
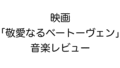
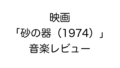
コメント