中級 楽曲分析学習パス 修了課題:比較分析とセルフチェック
► 課題の目的
・複数の楽曲を比較することで見えてくる音楽的特徴の把握
・作曲技法の共通点・相違点の分析力向上
・様式感の理解と分析的思考の定着
・自己分析力の向上
► 取り組み方
準備するもの:
・課題曲の楽譜(本記事でPDFを提供)
・A4用紙
・鉛筆・消しゴム
推奨学習時間:
課題:150分程度
・個別分析:20分 × 5曲
・比較分析:50分
自己採点:40分程度
► 課題内容
‣ 課題曲
次の5曲を「比較分析」し、それぞれの独自の点や共通点を数多く列挙すること。
課題曲:
・モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」
・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」
・モーツァルト「アレグロ 変ロ長調 K.3」
・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.4」
・モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.5」
‣ 課題曲楽譜
(PD楽曲、Sibeliusで作成)
原典版を定本としています。
異なるアーティキュレーションなどが書き込まれている版もありますが、今回の課題ではこれらの楽譜を使用してください。
モーツァルト「メヌエット ト長調 K.1」
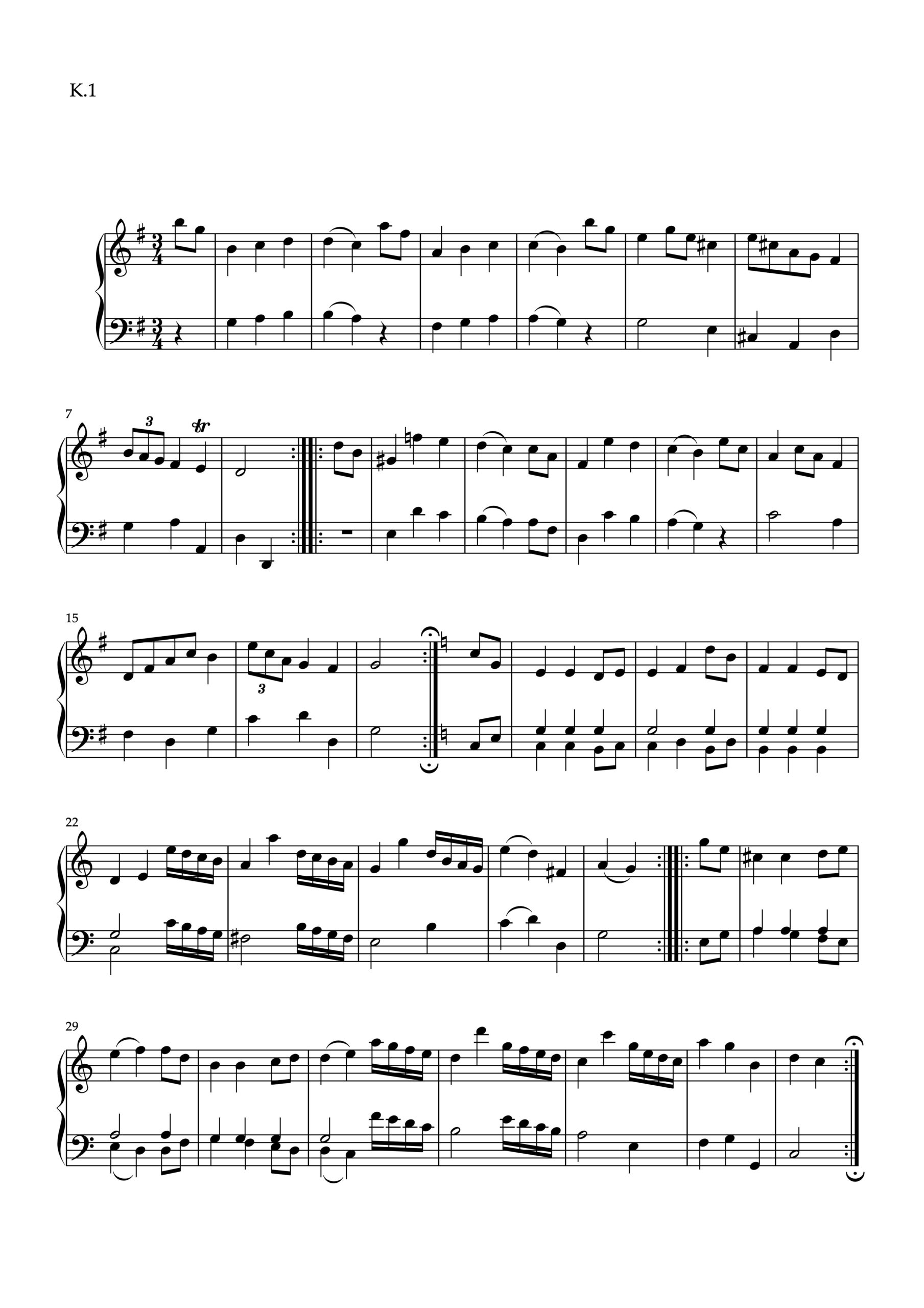
モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.2」
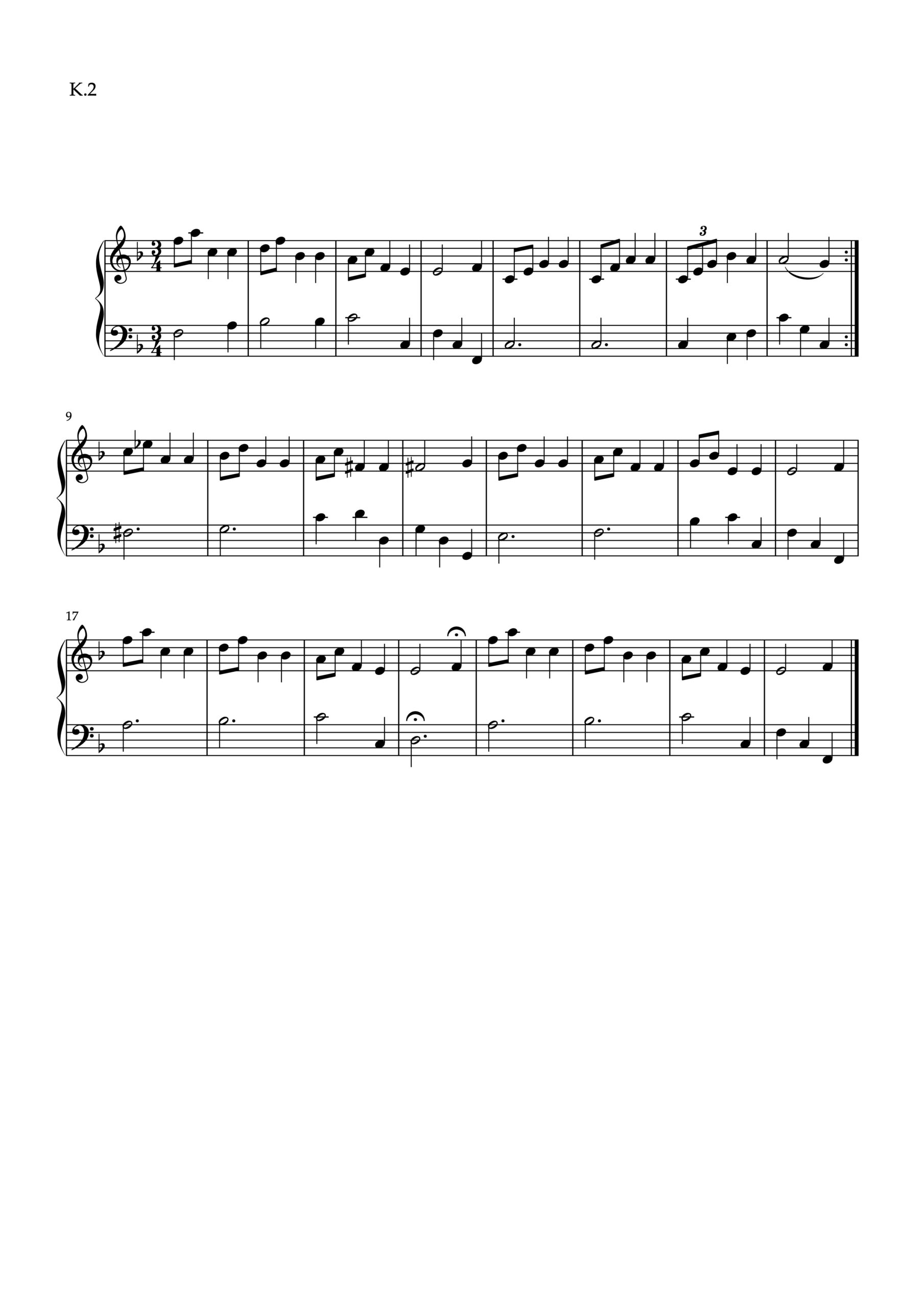
モーツァルト「アレグロ 変ロ長調 K.3」
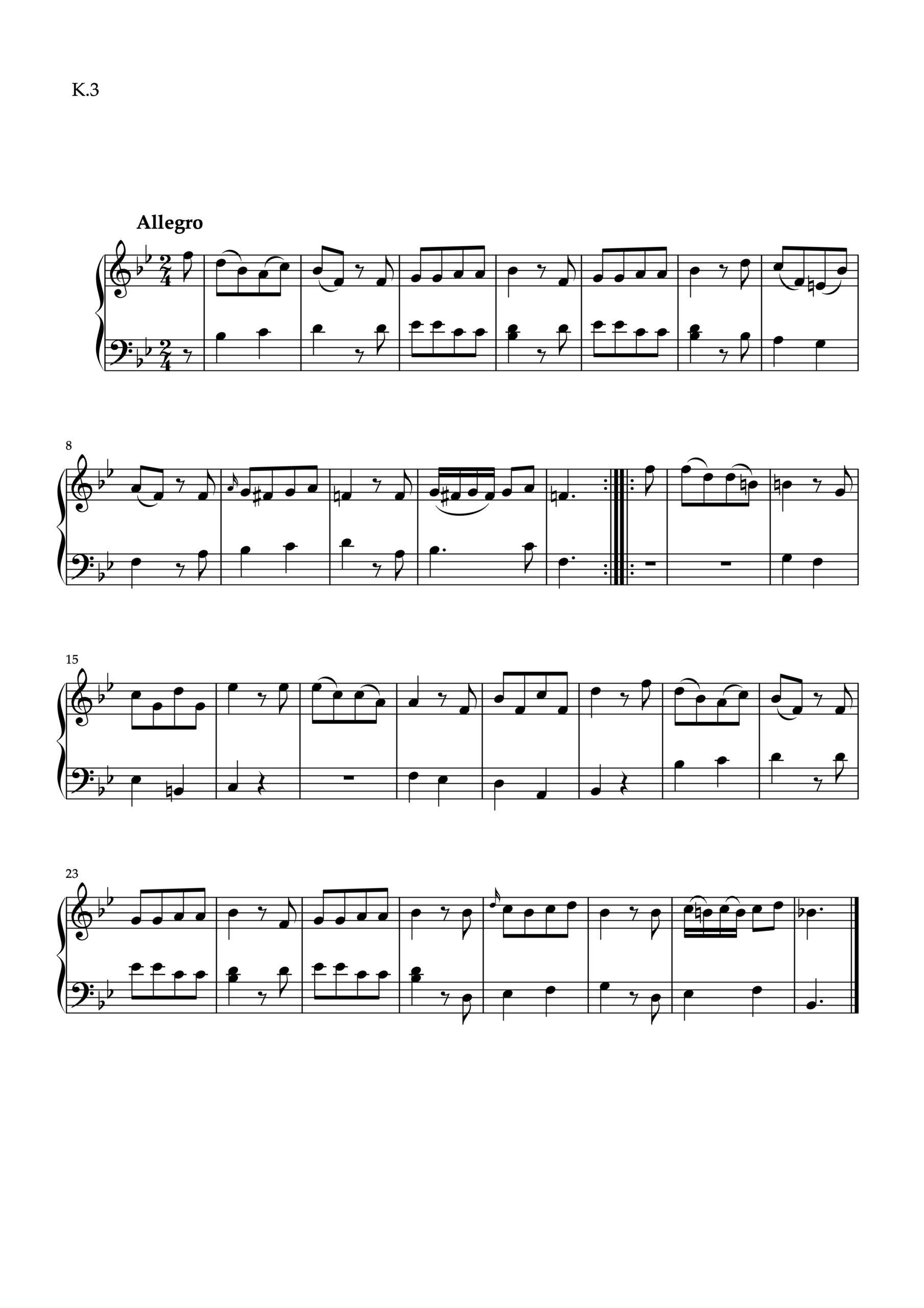
モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.4」
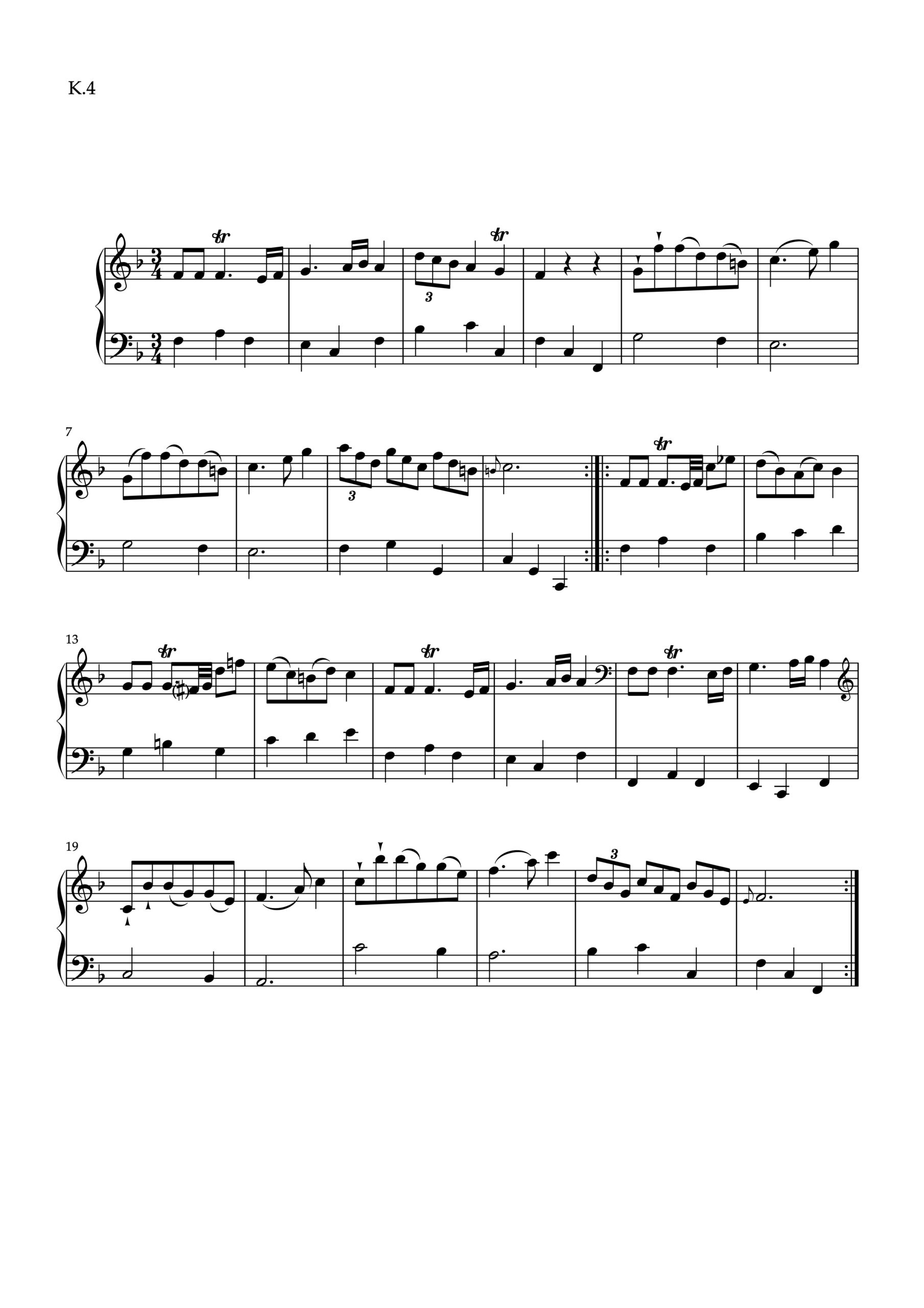
モーツァルト「メヌエット ヘ長調 K.5」
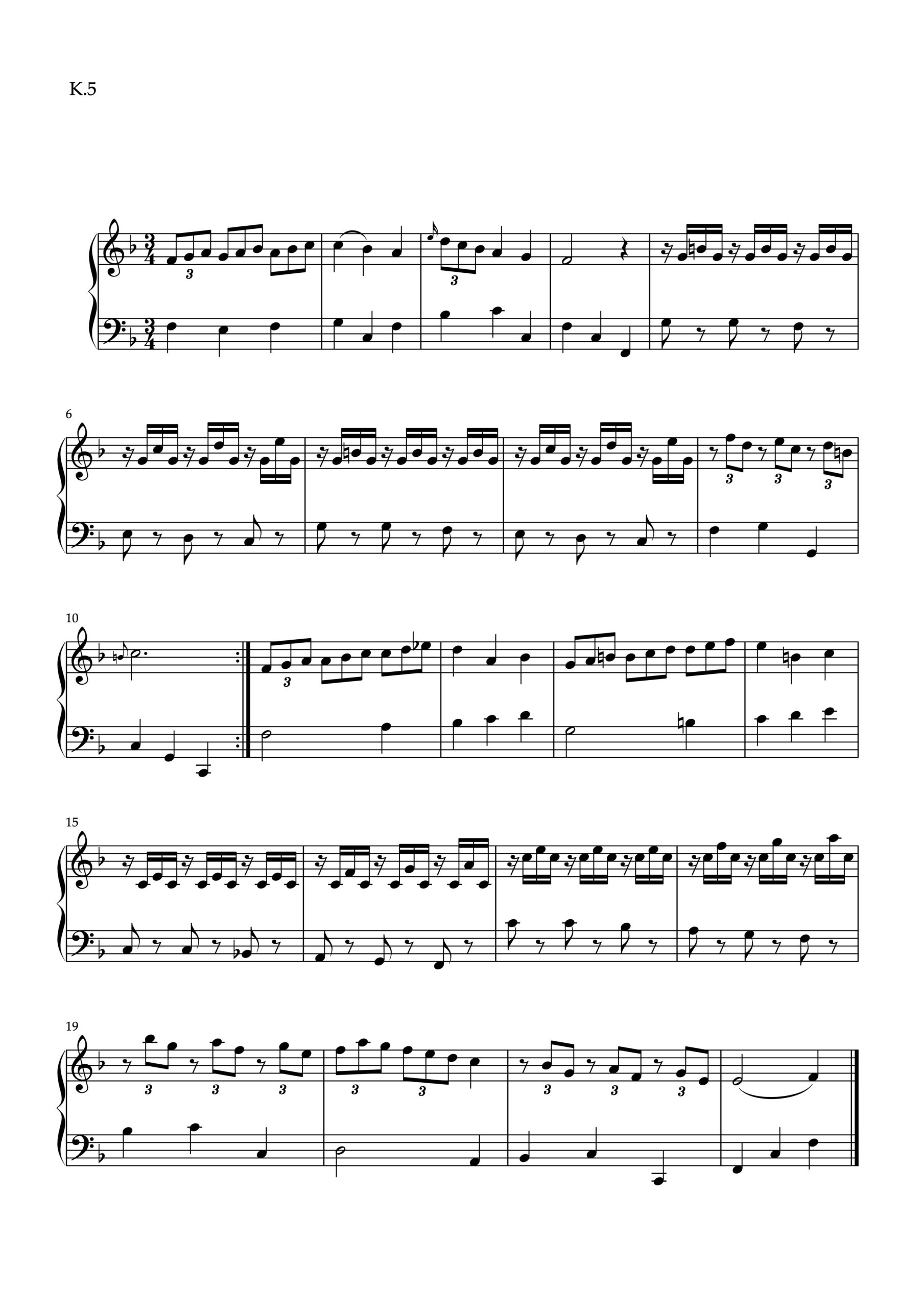
PDFで入手したい方は以下よりダウンロードしてください。
► 分析の観点
形式的特徴の比較:
・楽曲形式
・区分の方法
・終止形の使用
書法的特徴の比較:
・声部の扱い方
・動機の展開方法
・反復技法
和声的特徴の比較:
・調性計画
・転調の手法
・和声進行のパターン
記譜上の特徴の比較:
・アーティキュレーション
・装飾音の表記
・リズム表記
► 分析手順
Step 1: 各曲を順に細かく分析していく(20分×5)
・形式的特徴の確認
・特徴的な書法の抽出
・独自の表現技法の把握
Step 2: 分析結果をもとに「比較分析」に着手し、独自の点や共通点をA4用紙へまとめていく(50分)
・共通する特徴の整理
・各曲固有の特徴の整理
► 解答例
1. 全曲共通の特徴
形式・構造面
・K2-4は全て、三部形式
・どの作品も、偶数小節単位の明確な形式的区分がされている
・どの作品も、はじめのセクションは上属調で終止する
・どの作品も、カデンツによる明確な区切りがされている
声部構成・テクスチャー
・どの作品も、2声部中心の明快な書法
・どの作品も、左手にメロディがくるところは出てこない
・K.1とK.3にのみ、3声になる部分がある(独立した声部として3声になるのはK.1のみ)
作曲技法
・K.1とK.3のみ、アウフタクト中心の音楽
・どの作品も、同型反復の多用をしている
・どの作品も、短い動機の発展的使用がされている
・どの作品も、順次進行と跳躍進行の効果的な組み合わせ
調性・和声
・どの作品も、調号が少ない調で書かれている(うち3曲はヘ長調)
・K.1-3は全て、BセクションがⅡ度調で始まる
・K.4-5は、BセクションがⅣ調で始まる
記譜・表記
・どの作品も、細かなアーティキュレーションが中心であり、長いスラーは書かれていない
・どの作品も、原典版ではダイナミクスが書かれていない
・K.1とK.4には、記号によるトリルが出てくる
2. 各曲の特徴的要素
「メヌエット ト長調 K.1」の固有の特徴
・反復小節線上のフェルマータが出てくる(K.1のみ)
・メヌエット→トリオ→メヌエットの形をとっている(このトリオを別の楽曲として分類している研究もある)
・調号を変える転調が行われている(調合を変えない部分転調は、どの作品にも見られる)
「メヌエット ヘ長調 K.2」の固有の特徴
記譜的特徴
・音符上のフェルマータが出てくる(K.2のみ)
・コーダ的な終結部が付いている(K.2のみ)
和声的特徴
・11-12小節では、G-durのH音、g-mollのB音のいずれも出てこない
・9-10小節でg-mollを明示することで、11-12小節もg-mollとして機能
・この前後関係による調性確立手法は、K.3、K.5でも使用
「アレグロ 変ロ長調 K.3」の固有の特徴
形式・表記面
・Allegroというタイトルが付されている(K.3のみ)
・テンポ指示が書かれている(K.3のみ)
・2/4拍子(K.3のみ)
・3連符が出てこない(K.3のみ)
書法面
・書き譜によるトリルが出てくる(11小節目および、29小節目)
・c-mollの確立が前後の文脈から説明される手法(K.2、K.5と共通)
「メヌエット ヘ長調 K.4」の固有の特徴
リズム・音価
・32分音符が出てくる(K.4のみ)
構造的特徴
・5-10小節における6小節構造(7-8小節が付加的)
・オクターヴ下での同型反復手法(K.4のみ)
・15-22小節における対照的なオクターヴ反復
「メヌエット ヘ長調 K.5」の固有の特徴
リズム・音型的特徴
・拍頭が休符になった16分音符の表現(K.5のみ)
・3小節目の「装飾音+3連符」の独自表現
・拍頭が休符の3連符によるメロディ(9小節目)
構造的特徴
・K.4と同様の6小節構造(5-10小節)
・オクターヴ上での反復表現(K.4と共通)
和声的特徴
・前後関係による調性確立手法(K.2、K.3と共通)
► セルフチェックシート
評価の2層構造(100点満点)
1. 基礎的な分析力(60%)
・各曲の共通点を解答例の7割以上発見できたか(30%)
・楽曲固有の点を解答例の7割以上発見できたか(30%)
2. 応用的な分析力(40%)
・メインコースで学んだ専門技法を自分なりに活用できたか(10%)
・サブコースで学んだ知識を自分なりに活用できたか(10%)
・解答例にはない独自の視点を提示できたか(20%)
振り返りメモ(任意)
・一番分かりやすかったところ
・もっと知りたいと思ったこと
・次に挑戦してみたい曲
► アドバイス
・分からない部分があっても気にせず、できる部分から取り組みましょう
・音楽を楽しみながら分析することを心がけましょう
・「独自の視点を提示できたか」という部分を大切にしましょう
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
