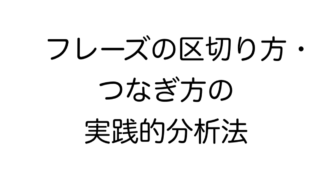 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 【ピアノ】フレーズの区切り方・つなぎ方の実践的分析法
ピアノ演奏でのフレーズの区切り方を、J.S.バッハのミュゼットとモーツァルトのソナタを例に詳しく解説。音をどのフレーズに属させるべきか、実践的な分析手法と演奏のコツを紹介します。分析の初級〜中級者向け。
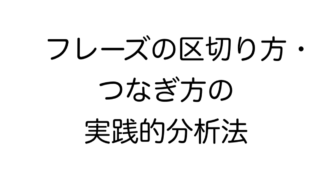 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 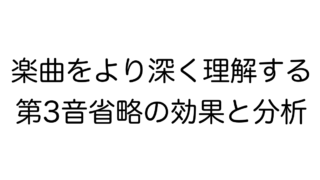 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 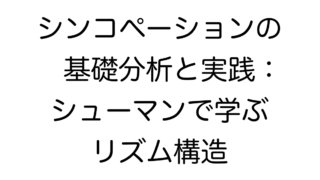 シンコペーション
シンコペーション 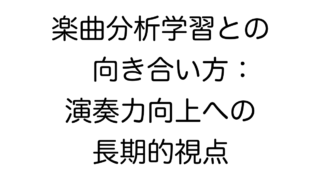 ‣ 楽曲分析パス
‣ 楽曲分析パス 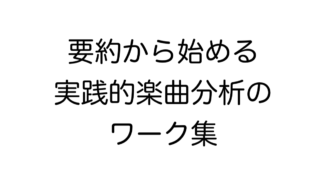 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 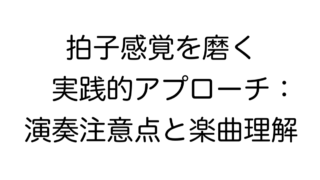 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 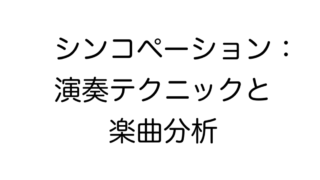 ‣ 基本奏法
‣ 基本奏法 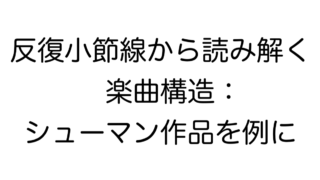 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 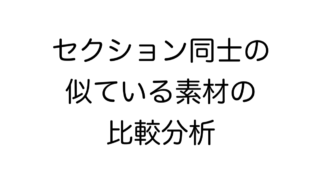 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 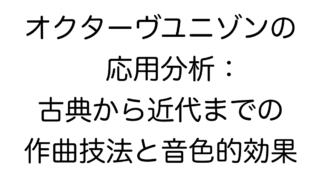 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法  楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 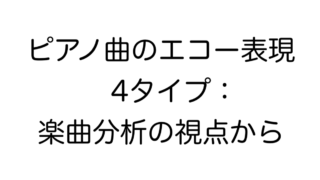 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法