買ったはいいものの、
積読になっている音楽書籍って
意外と多くあるのではないでしょうか。
少し読んでみて
興味をもてなかったりしたものは、
正直、ムリして読む必要はありません。
一方、明らかにためになると分かっている書籍だけども
重い腰が上がらなくて積読になっているものとは
ムリのない距離感で
付き合っていくといいでしょう。
付き合うポイントはいくつかあります。
音楽書籍に限りませんが、
まずはとにかく、出しっぱなしにすることです。
積読という出しっぱなしではなく、
すぐに手に取れる状態で
つまり、積んでいない状態で
出しっぱなしにしてください。
家での自分の定位置から
手を伸ばすだけで届く位置へ置くのがコツ。
まずは、これが出発点ですね。
もうひとつのポイントとしては、
読み進め方を細部化することです。
内容が専門的であればあるほど、
一気にすべて理解しようとすると
ほんとうに気が遠くなるんですよ。
ビニールの封がついているものであれば、
「今日は、封を開ける」
ここからでも構いません。
また、その次は
「序文を読む、目次に目を通す」
これだけでも構いません。
とりあえず、
毎日何かひとつでも、ほんの少しの量でも
前へ進めてください。
少しでもいいので
その代わり、ヘタに日を空けずに毎日進めてください。
とにかく、出しっぱなし。
とにかく、細分化。
この2点を実行すれば、
積読のタワーも少しは低くなるでしょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
X(Twitter)
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
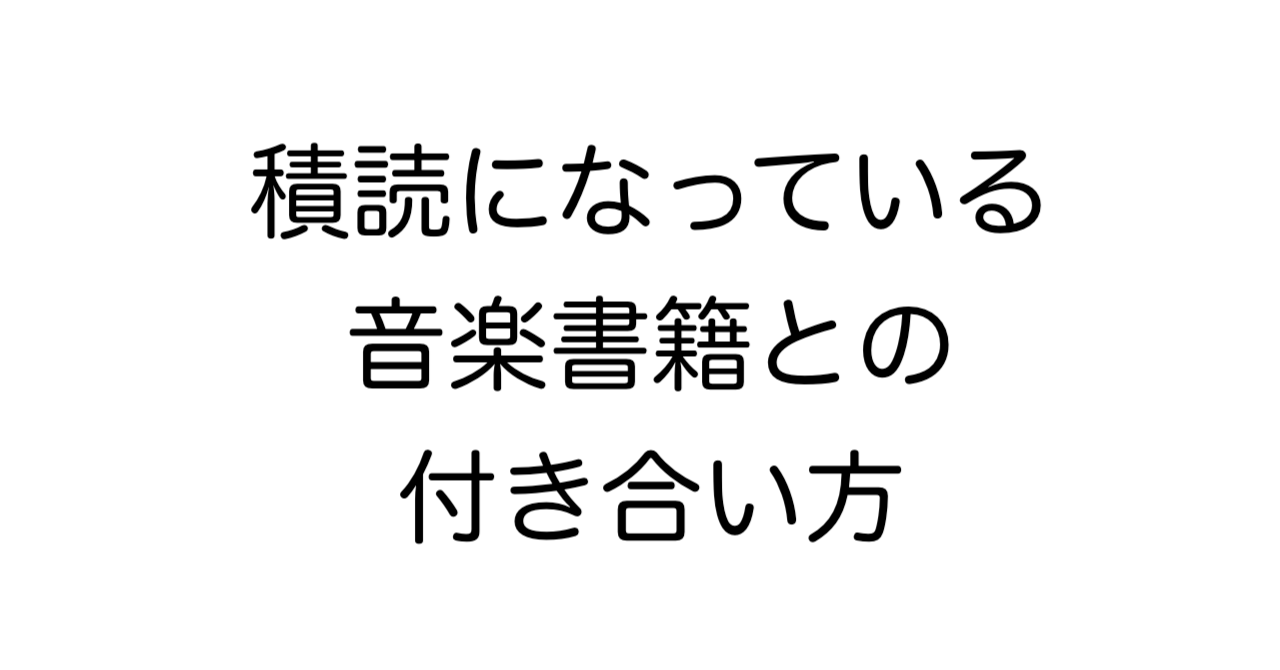

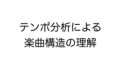
コメント