【ピアノ】先生に聞けない素朴な疑問10選:真面目に答えるQ&A集 vol.6
► はじめに
・「こんなこと、先生に聞いていいのかな…」
・「ググっても明確な答えが出てこない…」
こういった、聞きにくいけど実は気になるピアノ関連の疑問に、真面目に答えます。レッスンに通っている方はもちろん、スポット(単発)レッスンを受ける独学の方にも参考になる内容です。
関連記事:
► 質問集
‣ Q1. レッスン料を値切るのは失礼?
結論:値上げを断るのは理解できるが、値切りは失礼
教室側が値上げをする際、既存生徒の料金は据え置きで新規のみ値上げするケースが多くあります。ただし、既存の生徒にも値上げの相談が来ることがあります。
値上げを提案された場合:
・理由を確認し、できる限り応じるのが円滑な関係維持につながる
・どうしても難しい場合は、丁寧に事情を説明して断ることも可能
入会後の値切りについて
入会前に料金は明示されており、それに同意した上で入会しているはずです。入会後に値切り交渉をするのは、契約の前提を覆す行為として失礼にあたります。
‣ Q2. 複数の先生に習うのは失礼?
結論:現在の先生に許可を取ってからであればOK
内緒で別の先生に習うのは、最も避けるべき行為の一つです。複数の先生に習う場合は、必ず現在の先生に相談し、許可を得てから行動しましょう。
2人目の先生に習うべきケース
以下のいずれかに該当する場合のみ検討すべきです:
・今の先生から行くように提案された場合
・自分の意思で行く場合は、今の先生に納得してもらえた場合
納得してもらえるような理由がないのであれば、先生を増やす必要はないのです。
複数の先生に習いたくなる理由を見直す
率直に言えば、多くの場合は「焦り」や「判断の早さ」から来ています。
よくある誤解の例:解釈のアドバイスが欲しくて別の先生に行ったら、基礎的な奏法ばかり指摘されて曲が仕上がらなかった
これは、まだ別の先生の意見を求める段階ではないことを示しています。基礎が固まっていない段階では、複数の指導者から異なるアプローチを学ぶことで、かえって混乱を招きます。
まず考えるべきこと:
・なぜ、今の先生以外の指導を必要だと感じるのか
・自分は本当に複数の指導者から学ぶ段階に達しているのか
これらを冷静に見直すことが重要です。それでも必要と判断したなら、まずは今の先生のもとを離れ、完全に新しい先生に切り替えることも選択肢の一つです。
‣ Q3. 自宅練習の記録をつけてるけど、先生に見せるのは変?
結論:問題ない
練習記録を見せること自体は全く問題ありません。ただし、何のために見せるのかを明確にしておきましょう。
効果的な見せ方:
・「練習のバランスや時間帯について、アドバイスをいただけますか?」
・「練習の順番は適切でしょうか?」
このように、具体的な質問と共に提示すると有意義なフィードバックが得られます。
避けるべき見せ方
「たくさん練習している」ことをアピールするための提示は避けましょう。日頃のレッスンから、生徒の実力や練習量は伝わっています。演奏を聴けば、記録と実態のギャップはすぐに分かってしまいます。
‣ Q4. レッスン時間中、先生が他の音楽話ばかりするのは普通?
結論:普通だが、バランスが極端なら相談してOK
日常的な音楽談義を通じて、先生への理解が深まったりコミュニケーションが円滑になることは、レッスンの重要な要素です。
筆者の経験談
筆者は以前、60分のレッスンのうち40分以上が音楽談義、実技が15〜20分という指揮のレッスンを受けていました。先生の音楽経験からの知見、作曲家に関する雑学、指揮に関するこぼれ話、などをたくさん知ることができて、音楽そのものへの興味が深まりました。その会話の中で得た知見や経験談は、音楽への興味を深める貴重な学びでした。
考え方の違い:
・「60分のレッスン代を払っているから60分実技を」と考えるか
・「経験豊富な先生の知見を通して学べるのもレッスンの一部」と考えるか
これは個人の価値観によります。
バランスを改善したい場合
あまりにもレッスン時間が削られていると感じたら:
・丁寧に先生に相談する
・こちらから積極的にレッスン内容の質問を投げかけて、実技へ導く
補足:初級者のうちは、実技レッスンの時間を増やすことが、一定レベルに到達する近道になります。
‣ Q5. 作曲家や時代の背景は学ぶべき?
結論:積極的に学ぶべき
西洋音楽史を学んでも、すぐにピアノ演奏が上手くなるわけではありません。しかし、以下のような方には強くおすすめします:
・長く音楽を続けていきたい方
・上級レベルを目指す方
音楽史が演奏に役立つ例
モーツァルトのトリルの入れ方は、父親レオポルド・モーツァルトの教育が影響しています。そのため、ピアノ演奏者にもレオポルドが書いた「ヴァイオリン奏法」が参考になります。
このように、音楽史の知識が演奏解釈に直結するケースは数多くあります。
筆者の気づき
音大生時代、「音楽史を学ぶ時間があったら、1分でも多く作曲やピアノに向かいたい」と思っていました。しかし、卒業後に音楽史の重要性に気づきました。理由は:
・表面的な音符の再現を超えた演奏を目指し始めたから
・音楽に詳しい人物と深い会話をするために必要だと分かったから
専門家を目指さない場合でも、基本事項は学んでおくべきです。
西洋音楽史における「ピアノ音楽史の入門」に関しては、以下の記事で解説しています。
‣ Q6. 先生に言われたことを直さなかったとき、内心どう思っている?
結論:再度言わないだけで、気づいている
先生が同じ指摘を繰り返す場合、主に2つのパターンがあります:
・どうしても直すべきだから、嫌がられることを覚悟で繰り返し伝えている
・先生がよほど頑固な性格をしている
指摘されなくなった=先生が忘れている、ではない
「直さなかったけど、次のレッスンで指摘されなかったから大丈夫」と思うのは誤解です。多くの場合、先生は気づいています。そのうえで、「これ以上は言わないでおこう」と判断しているのです。
筆者も指導の現場で、絶対に直すべきことは何度でも指摘しますが、そうでない場合は1回しか言いません。
生徒の選択と指導者の気持ち
最終的にどのような音楽にするかは生徒が決めることです。しかし、現時点での知識や経験だけで判断し、アドバイスを聞き入れない姿勢が続くと、指導者としては虚しさや疑問を感じることもあります。自分でやりたいようにだけやるのであれば、もうすでにできるのです。
‣ Q7. 一つの曲に飽きてしまったらどうすればいい?
結論:楽しみ方を知る+楽曲の皿回し
ピアノ学習において、以下のどれに当てはまるでしょうか?
・譜読みも弾き込みも楽しく進められる
・譜読みは大変だが、弾き込みは楽しい
・譜読みは楽しいが、弾き込みが大変
意外にも、③のパターンが多い印象です。
なぜ、弾き込みが大変に感じるのか
これは、ダイエットに似ています。
ダイエットの例:
・開始直後:体重が着実に落ちて楽しい
・ある時点から:なかなか落ちなくなり、維持が辛い
ピアノに置き換えると:
譜読み:みるみる進む実感がある期間
弾き込み:進歩を感じにくい維持・微調整の期間
やっただけ進んだ感を強く感じる譜読みと異なり、弾き込みは地味で進歩が見えにくいため、大変に感じやすいのです。
弾き込みを楽しむ2つのコツ:
1. 毎日1つ、新しい発見をする
「弾き込みの段階でも、まだまだ発見がある」という意識を持ちましょう。弾き込みこそ思考停止しやすい時期です。意識的に学ぼうとする姿勢が、譜読みから弾き込みまで一貫して楽しむ鍵です。
2. 練習楽曲の皿回し
一曲に何時間も費やすのではなく、複数の曲を皿回しのように回していくことで、新鮮味を保つことができます。
‣ Q8. 先生に、発表会以外の「お披露目の場」を作ってほしいと頼んでもいい?
結論:OKだが、自分で探す力もつけるべき
本番の回数を増やしたい場合、発表会だけでは物足りないかもしれません。先生に相談することで:
・学習段階に合った本番の場を提案してもらえる
・門下生内での交流の場を設けてもらえる
といったメリットがあります。
自分でも探す習慣を
ただし、原則として自分自身でも本番を探していくことが重要です。そうすることで、将来を見据えた自立した学習ができます。
以下の記事では本番機会の見つけ方や増やし方を紹介しているので、参考にしてください。
‣ Q9. ピアノの前であくびが出ちゃう…失礼?
結論:大きな口を開けたあくびは失礼
あくびは生理現象なので仕方ありません。しかし、目の前で大きな口を開けてあくびをするのは失礼です。口を閉じたままあくびをする、もしくは手で覆うなど、最低限のマナーを守りましょう。
実例
フィギュアスケートの安藤美姫さんが海外で指導する様子がテレビ放送された際、堂々とあくびをした生徒を厳しく指導する場面がありました。本格的な指導の場では特に厳しいですが、どのようなケースでも、指導者の前で堂々とあくびをするのは失礼にあたります。
‣ Q10.「先生にがっかりされたらどうしよう」と思ってしまう
結論:行動マナーなどで不義理をしない限り大丈夫
「レッスンで先生にがっかりされたらどうしよう」という悩みはよく聞かれますが、演奏面での過度な心配は不要です。
先生は現実を理解している
生徒の実力や練習状況は、先生が最もよく把握しています。やるべき練習をしているのであれば、過度に物怖じせずに演奏を聴いてもらいましょう。
がっかりされるケース
演奏面よりも、行動マナーや約束を守らないなど、人間関係としての不義理があった場合です。こちらの方がはるかに重要です。
► 終わりに
先生に聞けないこと、ググってもあまり出てこないこと、たくさんあります。そんな小さな疑問を一つずつ解決していくことでピアノ学習を楽しくしていきましょう。
関連記事:
► 関連コンテンツ
著者の電子書籍シリーズ
・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)
Amazon著者ページはこちら
YouTubeチャンネル
・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)
チャンネルはこちら
SNS/問い合わせ
X(Twitter)はこちら
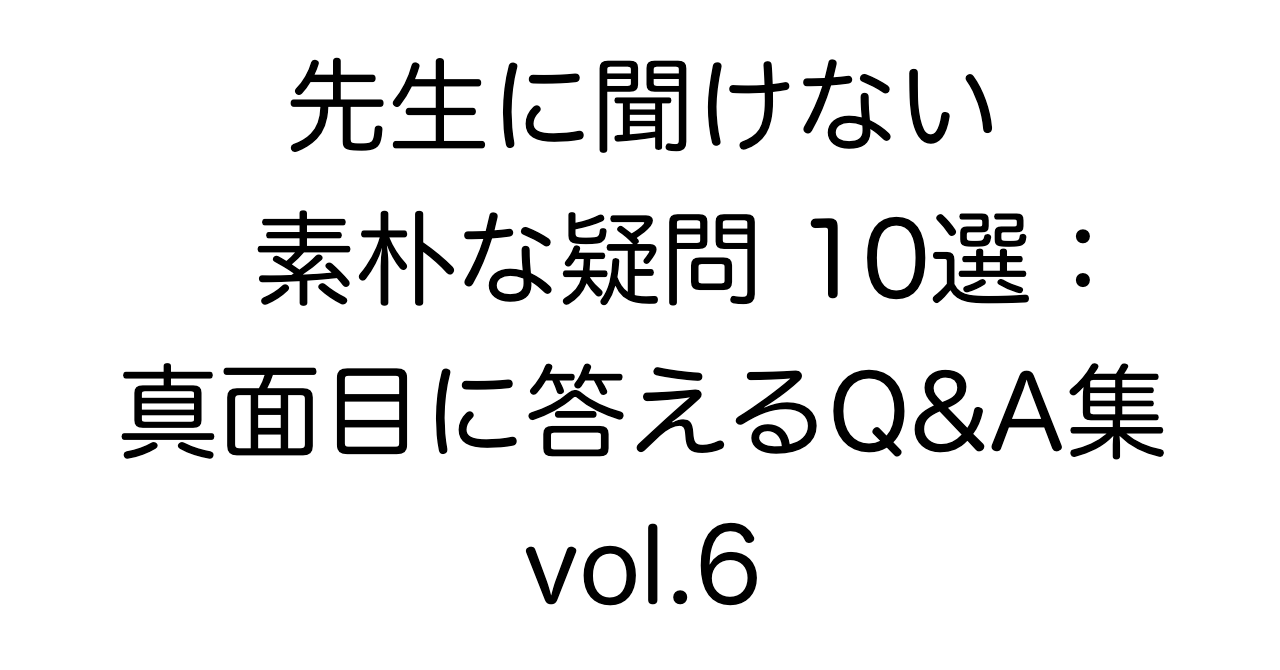
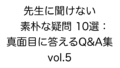
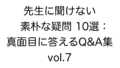
コメント