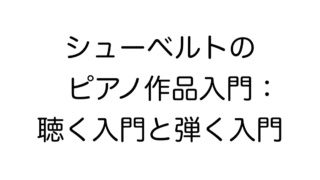 - シューベルト (1797-1828)
- シューベルト (1797-1828) 【ピアノ】シューベルトのピアノ作品入門:聴く入門と弾く入門
シューベルトのピアノ作品入門ガイド。聴く入門では「楽興の時」や「即興曲」から「最晩年の3大ソナタ」まで、弾く入門では「ワルツOp.18-6」など初心者向け楽曲を紹介。効果的な「聴き流し」アプローチも解説します。
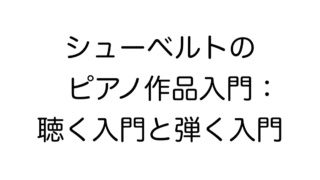 - シューベルト (1797-1828)
- シューベルト (1797-1828)  - 役に立つ練習方法 他
- 役に立つ練習方法 他 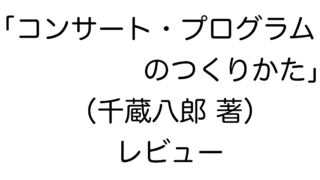 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 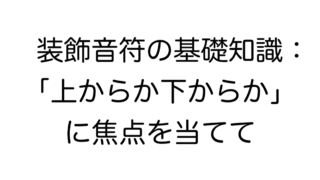 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 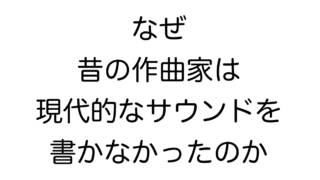 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 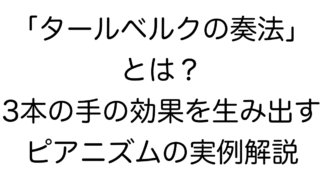 楽曲分析(アナリーゼ)方法
楽曲分析(アナリーゼ)方法 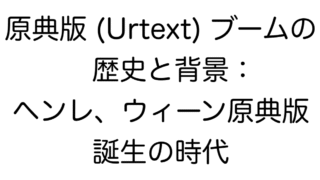 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造  音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 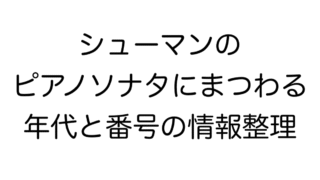 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 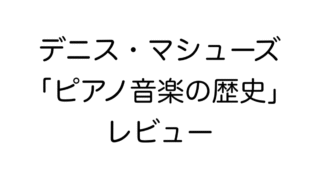 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造 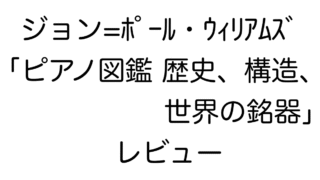 - ピアノ購入 / ピアノ引越し 関連
- ピアノ購入 / ピアノ引越し 関連 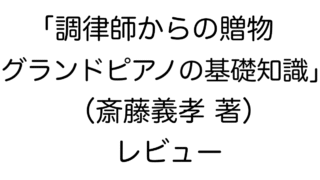 音楽史 / ピアノの構造
音楽史 / ピアノの構造