の記事中で、
以下の譜例とともに次のように解説しました。

シンコペーションを音楽的に演奏するコツは、
「くっている音(シンコペートしている音)に重みを入れること」
「くっている音(シンコペートしている音)に重みを入れること」
ここからが今回の内容。
譜例を見ると、
「この2例の場合のみ」と思ってしまう方が
いらっしゃるのではないでしょうか。
もしそうだとしたら、もう少し頭を柔軟にしてみましょう。
新たな譜例を見てください。

このように音価全体が広がった場合でも
基本的には同様の考え方ができます。
そして、
前回の記事では書きませんでしたが
「くっている音(シンコペートしている音)に重みを入れる」
と同時に、
「その次の短い音(譜例でいうと、それぞれの3つめの音)をやや軽く弾くようにする」
このようにすると、より音楽的。
くっている音が一層引き立つからです。
考えてみれば、
本来弱拍である「くっている音」が強調されなければ
もとより「シンコペーション」の定義から外れてしまいますよね。
今回の記事でさらに2つの例を挙げたことで
かなり多くのケースに対応できることでしょう。
頭を柔軟にすることで
さらに多くの似た事例に対応できるようになります。
あらゆる場合において
「どうやったらそのカタマリが音楽的に聴こえるのか」
ということを
常に考えて演奏するように心がけましょう。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!
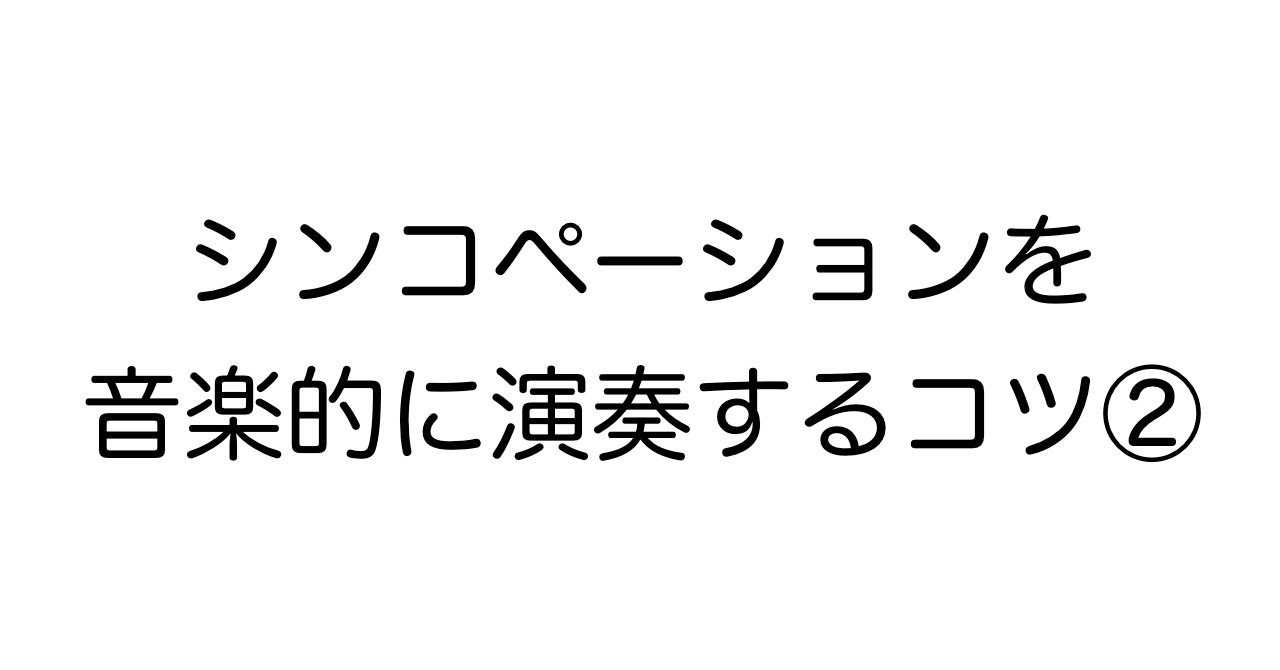
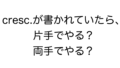

コメント