「旋律(メロディ)」というのは
多くの場合は「主役」としての位置付けです。
伴奏や対旋律よりも遠慮してしまうと
全体のバランスを欠くことになります。
しかし、
「旋律を強調しすぎない方がいい場合」
というのもあるのです。
ここで言う「強調しすぎない」というのは
「抑揚をつけすぎない」
ということも含めての意図です。
該当ケースとしては、大きく次の2つ。
2. 歌曲伴奏の場合
「その後に待っている ”より大切な旋律” を活かすために、
まだ淡々と弾いておいた方がいい場合」
というのは、
音楽を相対的に考えればわかりますね。
ダイナミクスに置き換えてみましょう。
「その後に待っている f を活かしたいのであれば、今書かれている mf はやりすぎないほうが相対的に f の箇所が活きる」
これと似た考え方です。
抑揚をつけた旋律というのは、かなりものを言います。
したがって、
いつでも抑揚をつけすぎてしまうと
しゃべりすぎになってしまいます。
◉ メロディに思い切り抑揚をつけて歌うところ
これらを使い分けると
それぞれの表現がどちらも活かされます。
こういったことは音楽を大きな視点でとらえないと
見落としてしまう内容です。
続いて「歌曲伴奏の場合」についてですが、
この場合は
「旋律を強調しすぎない」というよりも
「和音のトップノートを強調しすぎない」
といった方がより正確。
歌曲伴奏の場合、
和音が連続する伴奏型は多く
その場合は
和音のトップノートが旋律の役割を果たすこともあります。
しかし、
歌曲伴奏などの時には
あえて上の音などを強調しないほうが
歌手が歌いやすいケースが多いのです。
それは、
たとえ歌の旋律をユニゾンでなぞっていたとしてもです。
この辺りは
現場に合わせて歌手とやりとりしながら
適宜対応が必要となってきます。
もちろん、
間奏などで歌手が休んでいるところであれば
これには該当しません。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
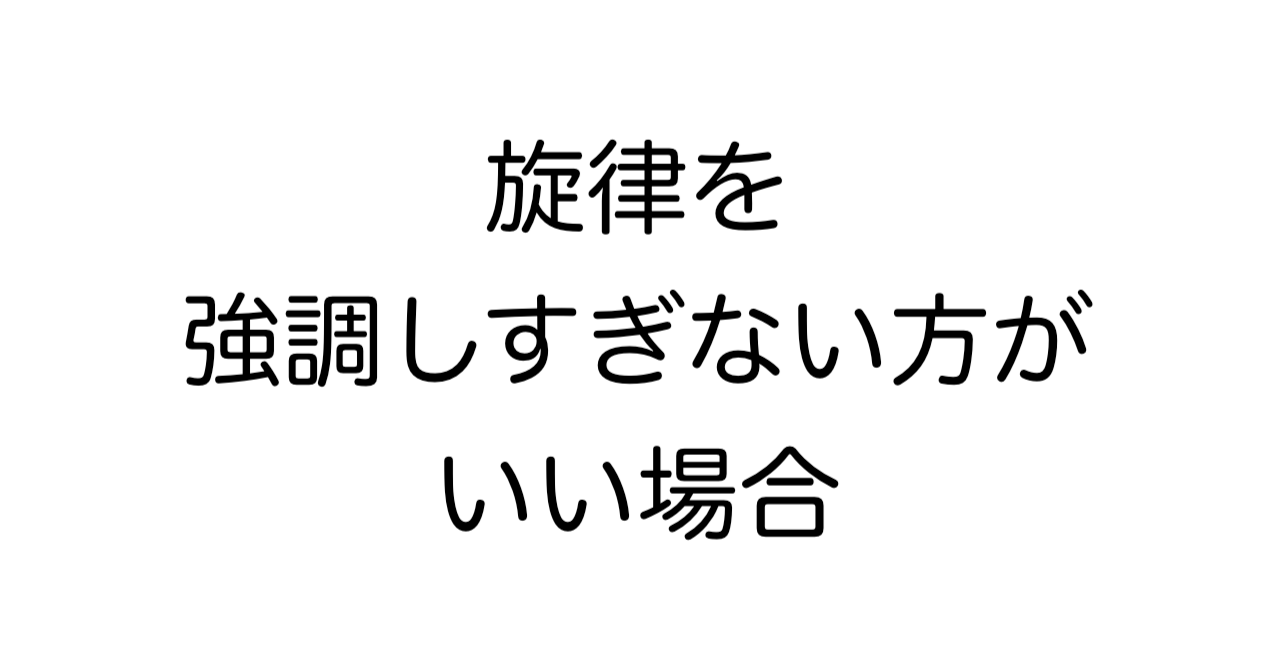


コメント