「3度」や「6度」が連続するハモリ
3度や6度の場合は、
「上方に位置する音をやや骨太に演奏する」
これが基本です。
ときどき、3度や6度のハモリでも
「下方に位置する音が主旋律になっているケース」
がありますので、
その場合は例外となります。
「4度」や「5度」が連続するハモリ
「連続4度」や「連続5度」は
空虚な硬い響きがします。
したがって、
作曲家はメロディックなラインというよりは
「マス(塊)」としてサウンドを聴かせたい時や
「ファンファーレ」のようなサウンドで
これらの音程を連続させることが多い。
その場合は、
「両声ともに同程度のバランスで演奏する」
このようにすると
むしろ硬いサウンドが引き立ちます。
上方に位置する音がメロディックなラインになっているケースも
ないわけではありません。
その場合は、
上声をやや骨太で演奏するようにしましょう。
つまり、
楽曲は多種多様ですので
音程ごとの「ある程度の傾向」をお伝えすることしかできません。
譜読みの際に
出てきたパッセージをその都度解釈して、
どのようなサウンドで演奏すべきなのかを判断していく必要があるのです。
「2度」や「7度」が連続するハモリ
これらは近現代の作品などでは頻繁に出てきます。
多くの場合は
メロディックなラインは想定されておらず、
「ぶつかったくすんだ響き」を
サウンドとして求められているケースがほとんどです。
したがって、
これらの音程が連続するときは
「両声ともに同程度のバランスで演奏する」
これを基本と考えておきましょう。
連続8度
「ハモリ」というよりは
通常の「オクターブユニゾン」です。
連続8度では、
◉ 下声をやや骨太に演奏するケース
◉ 両声ともに同程度のバランスで演奏するケース
それぞれを有効に用いることができます。
これについては、
以前に
という記事で解説していますので
あわせてご覧ください。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
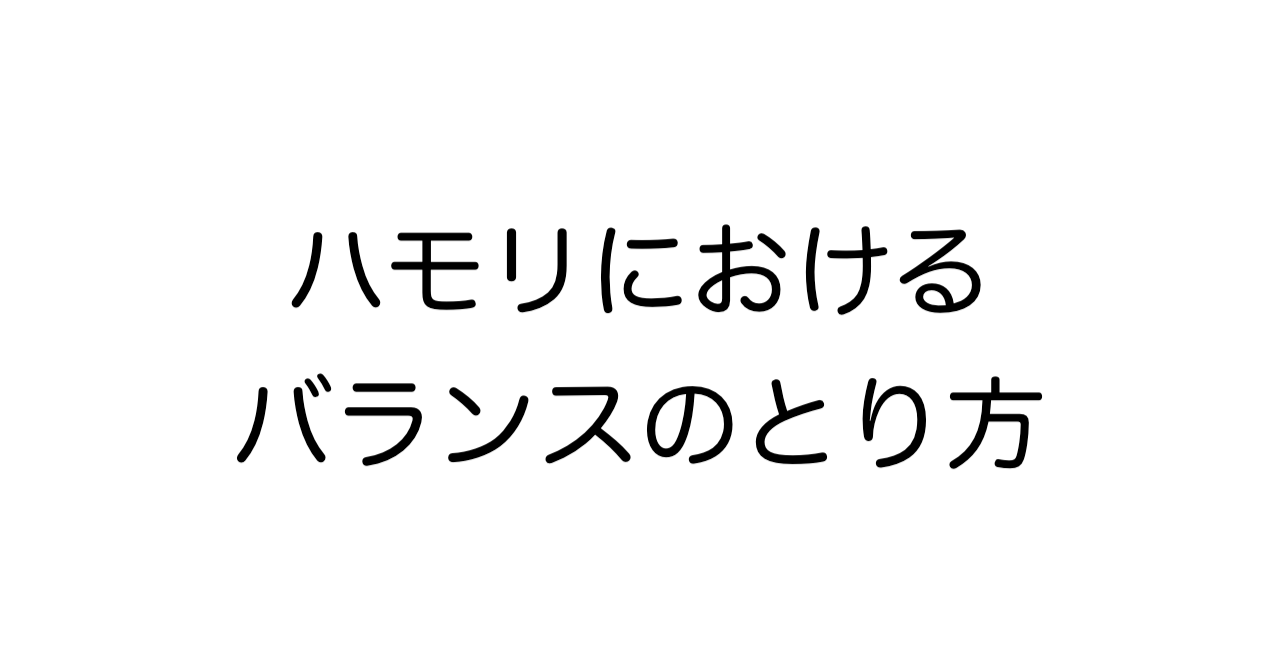
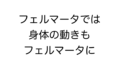
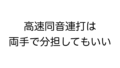
コメント