■書かれていない「強弱変化(松葉)」はどこまで補うべきか
① メロディのフレーズ表現のために
という記事の中で
「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本
と書きました。
つまり、
次の譜例の場合は
丸印をつけたEs音が大きくならないようにおさめます。
言い換えると
「Es音に向かって小さなデクレッシェンドの松葉が入る」
ということです。
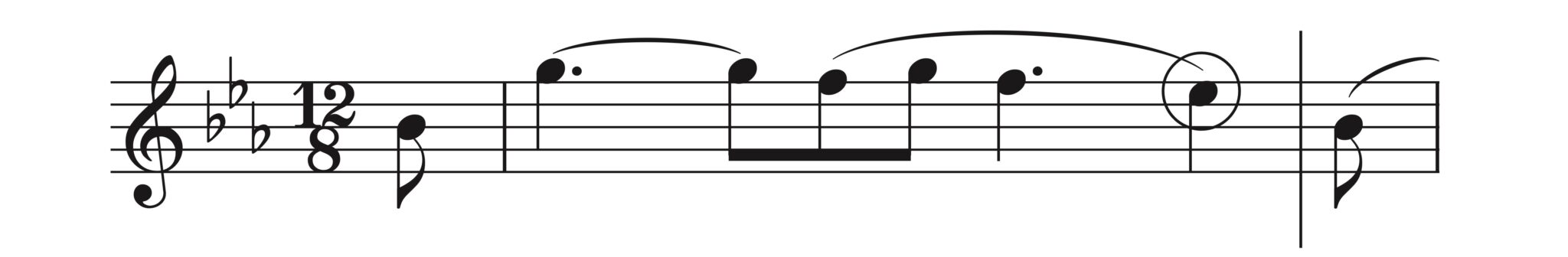
譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)
ここでいう「小さなデクレッシェンド」というのは
メロディのフレーズ表現のために補う松葉です。
原曲の楽譜には書かれていない内容であり
演奏者が補うものですよね。
「楽譜はレシピだからそのままではNGだよ」
というのは、
「こういったフレージングの処理はきちんとしないといけないよ」
ということでもあるのです。
② 重心へ向けた音楽の方向性をつけるために
という記事の中で
音楽が平坦になってしまう
と書きました。
モーツァルト「ディヴェルティメント K.136 より第2楽章」
譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)
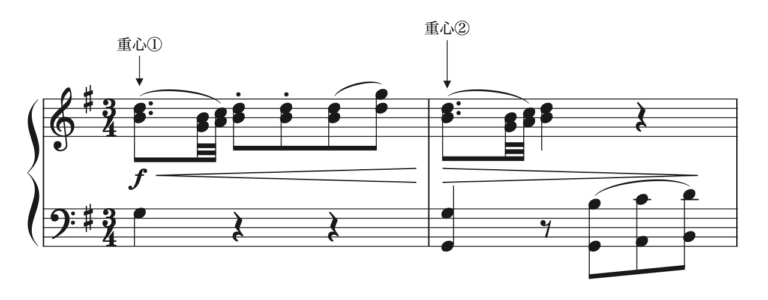
譜例に書かれている松葉は
演奏者が補うべきものを書き込んだだけで
原曲には書かれていません。
この例は、
メロディのフレーズ表現のためではなく
もっと大きなカタマリでの音楽の方向性を示した松葉です。
♬ 見落としがちな注意点
「強弱変化(松葉)」を補うべきシーンは
大きく以上の2パターンに分類されます。
一方、
ひとつ注意すべきことがあります。
「作曲家が ”実際に書き込んだ” ダイナミクスの松葉とのバランスを考える」
という点です。
ここまでに書いたように
「強弱変化(松葉)」は基本的に補うべきなのですが、
あまりにも大げさにやりすぎると
作曲家が ”実際に書き込んだ” ダイナミクスの松葉が活きなくなってしまうのは
想像に難しくないはずです。
音楽は相対的に聴かれるものだからです。
この辺りのバランスをとっていくのが解釈です。
それを磨くためにも
常に全体像で音楽をとらえる視点を持つようにしましょう。
【ピアノ】全体の構成はゼッタイに意識すべき
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
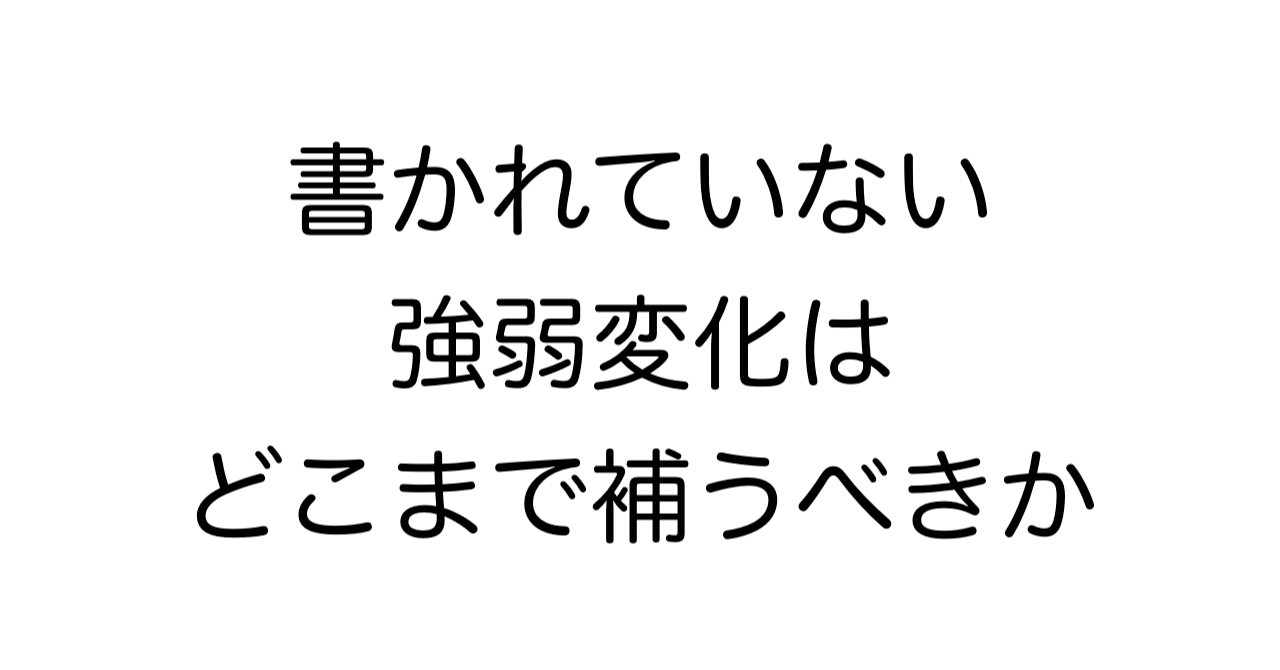

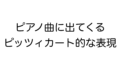
コメント