古典派の作品やショパンなどでも
楽曲の途中でカデンツァ風のパッセージが現れたりする。
たくさんの例がありますが、
例えば、
モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」
などでも登場します。
この作品では、
ピアノソロ作品であるにも関わらずカデンツァが登場することで
協奏曲のような雰囲気が出ていますね。
譜例(PD作品、Finaleで作成、カデンツァ部分)
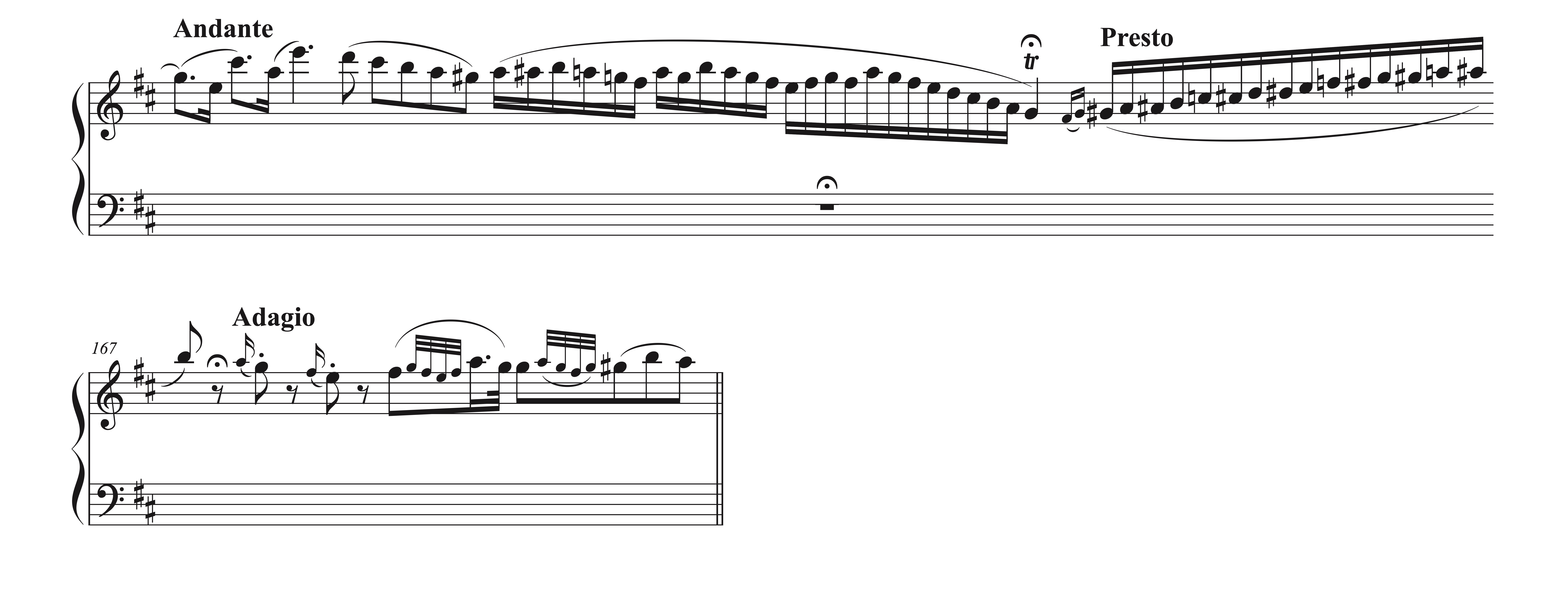
カデンツァの演奏では、
「比較的自由ではあるけれども完全に自由にしないこと」
これを考慮すべき。
上記の作品のカデンツァでは、
モーツァルト自身が
「4分音符」「付点4分音符」「8分音符」「付点8分音符」
「16分音符」「32分音符」「装飾音符」
といったような
さまざまな音価を書き残すことで、
カデンツァでありながらも大づかみのリズムは伝えています。
したがって、
自由さを持ちつつも
「拍の大づかみの感覚」
はもって演奏したほうが得策。
そうでないと音楽の骨格が歪められてしまいますので。
最終的に自由に弾くのはアリですが
まずは基本の骨格を把握しておきましょう。
作品よっては
音価が明確に書かれていなかったりと
カデンツァの大まかなリズムがわからないものもあります。
その場合でも、
「どこまでが区切りなのか」
というのを
自身の判断でも構いませんので
必ず決めておきましょう。
そうすることで
一応の骨格ができるということと、
万が一途中で暗譜がとんでしまっても
復帰できるポイントをつくることができます。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。
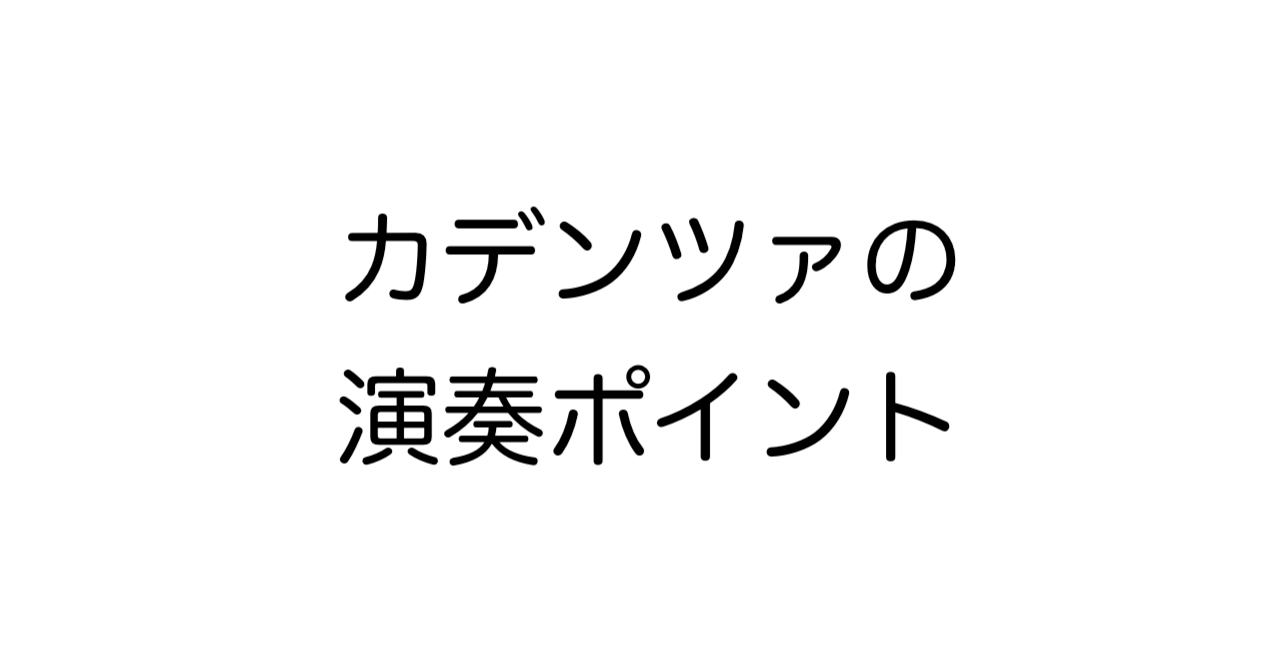
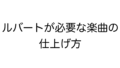
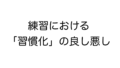
コメント