よく話題にあがるのは、
「臨時記号がシャープ系なのかフラット系なのかによって、音色を変える」
というもの。
「フラットが出てきたら音色を丸く」
などと考えている方も
いらっしゃるようです。
私の結論的には、
これに関してはあまり気にしなくてもよいと考えています。
「フラットになったから」
ではなく、
そこで柔らかい音色が欲しければ
そうすればいいだけのことです。
もちろん、
「調性」という観点でみると
各調におけるサウンドの差は大きい。
したがって、
調性自体が変化しているのであれば
音色を考慮すべきでしょう。
例えば、D-durとGes-durの響きはまったく異なりますよね。
また「異名同音転調」も
音色を変えるべきところの典型例です。
一方、
「臨時記号で一時的にフラットが出てきた」
という部分は
作曲家自身、もう少しアバウトに考えていることが多いのです。
例えば、次の譜例を見て下さい。
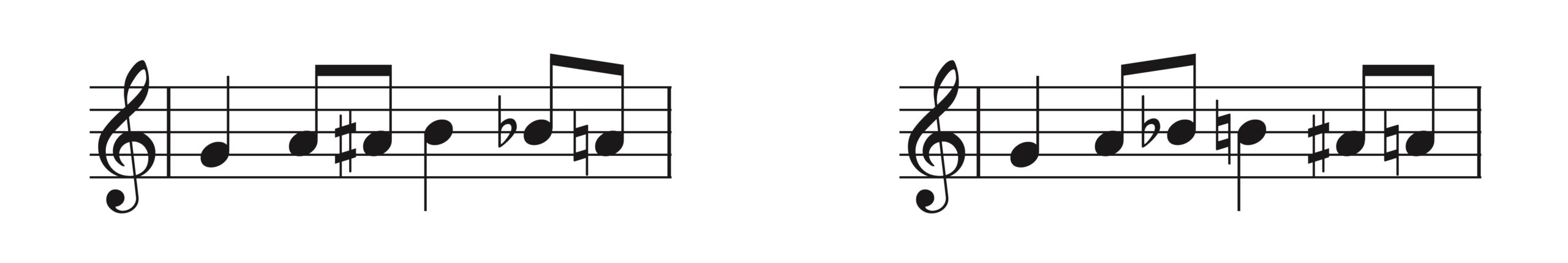
この2つの例の場合、
一般的に良いとされる記譜は「左の譜例」です。
例外はありますが、
◉ 半音で下がっていくときにはフラットを使う
こうした方が「読みやすく、音楽的」とされているからです。
しかし、
右の譜例のように記譜しても
絶対的な間違いとは言えません。
「その調の主音と属音はフラットさせないこと」
という楽典上の約束はありますが、
それ以外は
基本的には作曲家に委ねられていて
実際の楽曲ではさまざまな記譜が混在しています。
したがって、
こういったところで
「フラットが書かれているから、音色を…」
などと考えていると
解釈としておかしな方向へ行ってしまうのです。
はじめのうちは難しいかもしれませんが、
「自身がそこで音色を変えたいと思うかどうか」
これを参考にしたほうが
よい結果となるでしょう。
その感覚を磨くのは、
「臨時記号がシャープかフラットか」
ではなく、
「的確に楽曲分析をする力の積み重ね」です。
Amazon著者ページ
https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV
Twitter
https://twitter.com/notekind_piano
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg
筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、
200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。
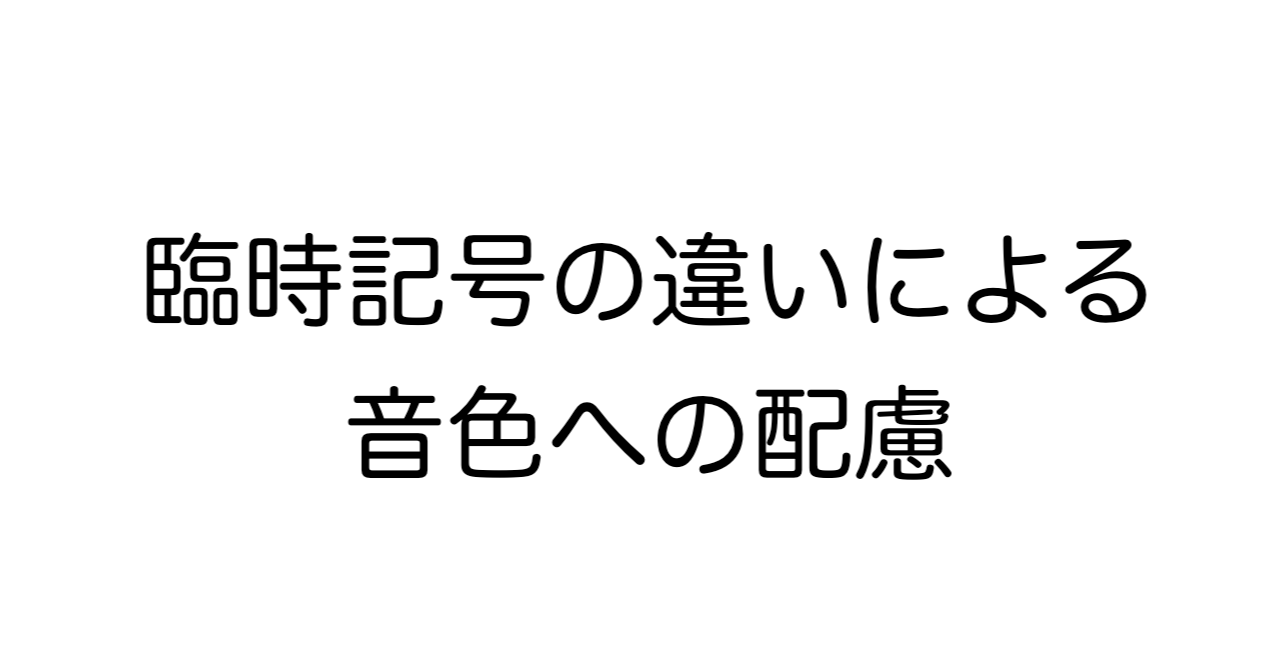
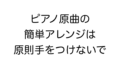
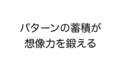
コメント